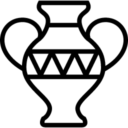こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「バーナード・リーチ」。
民藝には欠かせない人物、キーマンですね~。今も生き続けるリーチの魅力がたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
と、その前に、よろしければこちらもどうぞ(^_-)-☆
美の壺 「民藝のやきもの」<File540>お店や場所はドコ?吉祥寺の久保田直さんほか出演者情報もお見逃しなく!NHK美の壺「民芸(みんげい)の焼き物」
いざ、リーチ・ザ・ワールドへ。
【明日の #NHKBS #美の壺 】は #バーナード・リーチ
民藝運動に尽力したイギリス人芸術家 バーナード・リーチ。#濱田庄司 と見出した #スリップウェア。#映画監督マーティ・グロス が語るリーチ。
島根 #出西窯 で受け継がれるリーチの技。
人気の器、誕生秘話も!
18日 後5時30分 #BS pic.twitter.com/oQvlXsbTt5— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) March 17, 2025
目次
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
20世紀を代表するイギリス人の芸術家、バーナード・リーチ▽陶芸家、濱田庄司と共にイギリスで見出した美、スリップウェア▽フラワーデザイナーによるスリップウェアの楽しみ方▽戦前の日本でリーチが撮影した16ミリフィルムが、カナダ人映画監督によって甦る▽知られざるリーチのまなざしをテレビ初公開!▽リーチの薫陶を受けた島根の窯元。受け継がれる技と独自の工夫▽人気の器に隠されたリーチの物語<File630>
出典:番組公式ホームページ
【出演】井坂 浩一郎…ギャラリー店主/谷口 則子…フラワーデザイナー/マーティ・グロス…映画監督/多々納 真…出西窯 代表/井谷 和雄…出西窯 陶工
草刈正雄 木村多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「陶芸で結ぶ 東と西」
美の壺 井坂 浩一郎(いさか こういちろう)さん ギャラリー店主 東京・世田谷区
「GALLERY ST. IVES(ギャラリー・セントアイヴス)」は、イギリス陶器を扱うギャラリーです。
個性的なうつわがいっぱいあるのに落ち着いた雰囲気ですね。
店主の井坂浩一郎さんは、ロンドンの金融業界に勤め、いまではイギリスと日本をつなぐ橋渡しをしています。
ギャラリーのネーミング、「セントアイヴス」は、イギリスの南部の地名からきています。
井坂さんによると、イギリスは、2000以上の窯をもつ陶芸大国ですが、セント・アイヴスは、もともと焼きものの産地でなかったそうです。
芸術家が集まりだしたところに、支援者が陶芸の工房をつくりたいとバーナード・リーチを招へいしました。
1920年、リーチは、濱田庄司とともに海を渡り、西洋で初めて東洋式の登り窯をつくりました。「リーチ工房」のはじまりです。
オーブンに入れて調理ができる日常づかいの器に注目をし、作陶をしている間に液状の化粧土で装飾をほどこす「スリップウェア技法」を見いだしました。
東と西、濱田とリーチは、名もなき陶工の手仕事による美の追求がはじまりました。井坂さんは、リーチと濱田は、人間の手で表現する温かみを残していきかったのだろうと話してくださいました。
ギャラリー・セントアイヴスは、木曜〜日曜の12時〜18時に営業しています。月〜水は、お休みされています。お間違えなく。
<todo>自由が丘のギャラリーセントアイヴスに行って、濱田窯三代とリーチ・ファミリー展を見たい。1/14まで。 pic.twitter.com/1VrWtuzwx5
— 千樹本 一 (@sakimotohitotsu) December 10, 2017
(千樹本 一@sakimotohitotsuさん、アップありがとうございます。)
美の壺 谷口 則子さん フラワーデザイナーとスリップウェア
民藝では欠かすことのできない装飾「スリップウェア」には、どんな魅力があるのでしょうか。
ノンフローラルスタジオ代表でフラワーデザイナーの谷口則子さんは、集めたスリップウェアのうつわに野の花をあしらいます。
生けている大ぶりの花器は、リーチの孫にあたるフィリップ・リーチの作のもので生ける植物によって全く異なる表情を見せてくれます。リーチらしさが感じられる花器ですね。
谷口さんは、ツルウメモドキの枝のおもしろさをいかしながら、土から育まれているものを表現できればと考えていけてます。
イギリス特有の赤土から生まれた器が日本の自然と調和して東西のコラボレーションですね。
庭では、ハーブや野草を栽培して四季を通じて組み合わせます。
虫食いのある草や茎といった自然そのものを土色の茶色いうつわでいけることで、より自然になったと谷口さんは語ります。
マグカップにチョコレートコスモスを、片口には、雑草を入れます。
もちろん、本来の用途とはちがいますが、うつわ自体に命があり、力を感じさせてくれてつくられたものの尊さを感じさせてくれるのです。
外交官の家のフラワーデザイナーの谷口則子さん。民芸のバーナード・リーチ関係の英国工芸家の器と花のコラボ。http://t.co/xAORJ6VREN pic.twitter.com/61MV8Fz8lZ
— 富士山888 (@nekosachi803) June 12, 2014
(富士山888@nekosachi803さん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「物に宿る命」
美の壺 映像が語るバーナード・リーチ
バーナード・リーチは、明治から昭和にかけ15回、日本へ訪れました。当時の映像が残され、その人物像が垣間見ることができます。
それは、それは!貴重な資料ですね。
リーチは、島根県松江市にも訪れ、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の住居跡へ訪れています。
アイルランド人とギリシャ人の両親をもち、日本へ帰化したハーンは、日本の文化を世界に発信しました。
リーチと相通じるものを感じます。ハーン同様、日本文化に心酔したリーチにどのような思いが到来したのでしょうか。
バーナード・リーチは、1887年、イギリス人の父母の間に当時のイギリス領の香港で生まれます。
母は、出産で死去、日本にいた母方の祖父母に4歳まで育てられます。
その後、父の再婚を機に帰国、22歳の時、自らの意思で日本に居を構えました。リーチが陶芸を知ったのも日本です。
1914年、上野であった東京大正博覧会で楽焼の絵付けを体験、六代目尾形乾山に陶芸を学び陶芸家として道を歩むことになります。
やがて、濱田庄司、柳宗悦と出会い、民芸運動をおし進めました。日本の陶芸との出会いがリーチの人生を突き動かしたのです。
【読書記録】「リーチ先生」(原田マハ)
日本の陶芸に魅せられ日英の懸け橋になろうとしたバーナード・リーチとその周辺の人たちの物語。震災や戦争もあった時代だがそれらの描写は少なく、主に彼らの芸術に向き合う姿勢が描かれる。芸術家は強いのだ。 pic.twitter.com/NdlxtXU5w0— 恵の素ヒデキ (@sweet_enocci) March 19, 2025
(恵の素ヒデキ@sweet_enocciさん、アップありがとうございます。)
美の壺 マーティ・グロスさん 映画監督
1934年、リーチが日本を旅した様子を撮影した16ミリフィルム映像が残されています。
カナダ在住の映画監督、マーティ・グロスさんは、リーチのフィルムをデジタル化した映像をアーカイブとして保存しています。
マーティさんがリーチに出会ったときは、すでに88歳になっていました。目が不自由で寂しそうな様子でしたが、日本の話をするのが好きだったそうです。
リーチは、自ら撮影した映像を残して欲しいとマーティさんに託しました。
当時を振り返るリーチの肉声を映像に乗せて記録映画にしました。今回、特別にTV初公開されました。
映像には、濱田庄司がイギリス帰国後に栃木県益子にひらいた窯での作陶の様子が、細かに撮影されています。
健やかで美しい日用品が誕生するのを見届けたリーチは、技を身体にしみこませている陶工たちの姿に驚いたことが伝わります。
イギリスでは、すべてリーチが教えていました。
毎日同じものをつくっては上達し、よい物ができあがり、やがて、陶芸を学ぶ人がセントアイヴスへ訪れ世界へと広がりをみせました。
リーチは自らを「伝達人」だと語り、マーティさんもリーチから手仕事の精神を受け継いでいます。
「説明はいらない、ただその物を見よ!」それがリーチの教えです。
マーティグロスさんと、奈良散策。
柳宗悦、バーナードリーチが残した映像をデジタル化し、尚も編集した貴重な映像をたくさん観せて下さいました!
着物で生きる日本の姿。
1930〜1940年代の日本。
多くの人に観てもらいたいと思いました。奈良でも上映会出来たらいいな。https://t.co/8WbKcWrvwU pic.twitter.com/efSgYggR46— 御仕立処 波衣蓭 美波 (@minamiwasai) July 24, 2022
(御仕立処 波衣蓭 美波@minamiwasaiさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「器を師とせよ」
美の壺 井谷 和雄(いたに かずお)さん 陶工 島根県出雲市
バーナード・リーチゆかりの地、島根県出雲市の出西窯(しゅっさいがま)」。
1947年に、農家の若者5人で立ち上げました。現在も16人の陶工が、地元の土で日常づかいの器をつくっています。
リーチは、1953年〜64年の間に出雲へ3度訪れています。訪れたときに器づくりを指南しました。そのひとつが「コーヒーカップ」です。
陶工の井谷和雅さんは、20年以上、毎日ひたすらコーヒーカップをつくり続けています。1日につくる数は、およそ100個です。
1日に100個もつくるのですか。100個も⁉︎
数をつくることで身体に覚えこませます。井谷さんの作業場には、見本図があります。
それは、リーチがスケッチした写しで、井谷さんが、コーヒーカップを担当するようになった時、見本をコピーしてもらいました。以来、貼っています。
20年経つと、上手くなったり、力が弱くなったり、変化がありますが、見本図は変わりません。ギャップを埋めるものとして、井谷さんには大事なものです。
ブレないスピリットですね。
口当たりは、なめらかに、取手は、リーチ直伝のウェットハンドル技法です。取手に親指を置いて休ませる細やかな細工もあります。リーチの教えが生きてますね。
いかに持ちやすく、飲みやすく、味わえるか、普段使いしてもらうことがいいのだと井谷さんは、語ってくださいました。
出西窯の定番、リーチ型の美しいカップ&ソーサー。ほしかった呉須がオンラインストアに再入荷したので購入。愛用している黒釉よりも少しスリム。バーナード・リーチが残した言葉「触れたその手に喜びがあるか、触れた唇に温もりがあるか」をいまも大切に継承しているそう。さっそくコーヒーを淹れて。 pic.twitter.com/4pm7JlfUNQ
— hiroyann (@hiro_n78) August 26, 2020
(hiroyann@hiro_n78さん、アップありがとうございます。)
美の壺 多々納 真(たたの しん)さん 陶工
リーチが出西窯を訪れて70年。
窯を立ち上げた一人、故・多々納弘光さんの自宅には、リーチの資料が残されています。特別に長男の多々納真さんにみせていただきました。
これはお宝です!
『リーチ先生御指示図案 写本』とあります。実際のスケッチは、1979年に窯が火事となり焼失しました。弘光さんが、薄い紙をのせてコピーをしたものが残っているのです。
弘光さんや陶工、関わった人々の思いがそうさせたのでしょうね。リーチは数日の滞在で朝から晩まで指導をしたそうです。
情熱を感じますね。
当時の田舎の農村には、コーヒーカップやピッチャーは見たことも聞いたこともない人がほとんどでした。
最初は、何度やっても思ったようにつくれなかったが、少しずつできるようになり、それを見てリーチ先生は喜んでくれたと、多々納真さんは、父・弘光さんから聞いているそうです。
日本人の生活様式の変化を見すえて、洋食器の技術を伝えたリーチ。ある時、多々納さんは、聞いたこともない「グラタン皿」の注文に戸惑いました。
その造形の糸口となったのがコーヒーカップの取手の技法です。
コーヒーカップの取手を、土鍋のように皿の持ち手に応用させました。従来からある日本の造形と、洋食器のわざが融合し誕生しました。
まぁ、なんて素敵な出会いなんでしょう!風土や人の手から生まれる日常の器には今も、これからもリーチの息づかいが宿っています。
最近発売された『出雲の民窯 出西窯 民藝の師父たちに導かれて六十五年』多々野弘光(ダイヤモンド社)。
あのユニークな開窯の様子などがご本人によって語られています。http://t.co/mWzaLoLdi8 pic.twitter.com/EugMh7023J— TSUKAPONG (@hack_shon) March 3, 2013
(TSUKAPONG@hack_shonさん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。