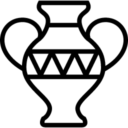こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「日本の美を見つめて ブルーノ・タウト」。日本の美意識を伝えたブルーノ・タウトは本にもなっていますよね。ブルーノ・タウトが、愛したニッポンがたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、タウトワールドへ。
📺[BS]今夜9時15分
「#美の壺」
日本の美を見つめて ブルーノ・タウト#桂離宮 や #伊勢神宮 の美を称賛した、
ドイツ人建築家 #ブルーノ・タウト
日本に唯一残る建築や、モダンな工芸品から、
タウトが見出した「日本の美」に迫ります👀▼HPhttps://t.co/U1C2cfCNIJ#nhkbs #草刈正雄 #木村多江 pic.twitter.com/Xw8ifrs4mK
— NHK BS (@NHK_BS1) October 17, 2025
目次
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
桂離宮や伊勢神宮でタウトが見つけた“究極の美”。建築家・隈研吾さんが、父から譲り受けたタウトがデザインした小箱とともに語る!▽タウトが日本で大半で過ごした平屋で、タウトの人物像に迫る!▽日本に唯一残るタウトの建築。西洋と東洋のデザインを融合させた美学とは?!▽小さきものに無限の広がり…タウトが手がけたモダンな工芸品▽タウト工芸の技を唯一受け継ぐ職人の手仕事!<File645>
出典:番組公式ホームページ
【出演】マライ・メントライン…ライター・翻訳家 江原 幸太郎…群馬県立歴史博物館 学芸員 隈 研吾…建築家 前島 美江…西上州竹皮編み伝統工芸士 廣瀬 正史…達磨寺住職
草刈正雄 木村多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「泣きたくなるほど美しい」
美の壺 隈 研吾(くま けんご)さん 建築家
日本を代表する建築家 隈研吾さんが登場します。
主に木材を使い、和をイメージしたデザインは、「和の大家」と称され、近年では、2019年に竣工された国立競技場の設計でも知られています。
隈さんの建物は、いろんなところで見かけますね。特に美術館、癒される空間ばかりですね。
隈さんが建築家として大きな影響を受けているのが、ドイツの建築家 ブルーノ・タウト(1880-1938)です。
隈さんが、タウトを知るきっかとなったのは、子どもの頃、父がみせてくれた木箱でした。今となっては、父から譲り受けた、大切な宝箱です。
建築学科に進み、おもしろい建築家だと興味を持ちました。
隈さんが、タウトの中でいちばん好きなのは、「関係の中に豊かさある」ということでした。
それは、自然との関係であったり、コミュニティだったり、関係の中から建築をつくることを学んだそうです。
隈さんは、タウトについて20世紀最初のモダニズムだと評します。形は、シャープでありながら広く環境や時間を考えて表現をしています。
近代建築の勢いがある時にそれを否定し、時代の先を歩んでいることに驚きだと語ってくださいました。
7/11付の日経でドイツの建築家ブルーノ・タウト氏の作品が紹介されていました。生駒のまちづくり鼎談で、建築家の隈研吾さんが見せて下さったタウト氏デザインの木の箱。続き→ https://t.co/raqIt1GU9Q#ブルーノ・タウト #隈研吾 #中谷ゆりこ #生駒市 #日経新聞 #日本のグローカルアート十選 pic.twitter.com/Q1R2tz6Xz5
— 中谷 ゆりこ (@yuriko_nakatani) July 12, 2019
(中谷 ゆりこ@yuriko_nakataniさん、アップありがとうございます。)
美の壺 ブルーノ・タウトが愛した建物 「伊勢神宮」三重県伊勢市 「桂離宮」京都市西京区
昭和8年、ブルーノ・タウトが日本にやってきた頃、街には西洋風の家が建てられたはじめた時代でしたが、タウトは、日本古来の建築の美しさに目を向けます。
来日から5ヶ月後、訪れた伊勢神宮について、著作『日本美の再発見』(篠田英雄 訳)で、
「悠久なこの国土と国民とを創造した精神の宿る神殿として…はるか古えに遡り、しかも材料は、常に新しいこの荘厳な建築こそ、現代における最大の世界奇蹟だ。」
と語っています。
また、タウトを「建築における関係性の重要さ」に気づかせた場所が、江戸時代、八条宮智仁・智忠親子によって建てられた「桂離宮」です。
「泣きたくなるほど美しい」とほめたたえました。
桂離宮は別荘です。ヨーロッパでいうとパレス(王宮)のようなものですが、パレスとは思えないほどの粗末なものだとタウトは感じながらも庭との関係性において豊かさがありました。
建物、庭石、池、樹木などそれぞれが独立しながらも相互関係を築いていることにタウトは気づかされ「粗末だが美しい」という新たな評価基準を打ち出しました。
『画帖桂離宮の回想』には、その感動を27枚のスケッチにしています。建物と庭の精神的なつながりついて思いをめぐらせています。
【ブルーノ・タウト 画帖 桂離宮(限定800部)】
桂離宮の機能美に強く打たれた建築家 ブルーノ・タウトがその感動をみずから描き留めた画帖を、タウト生誕100年を記念し800部限定で復刻したもの。https://t.co/juLSQgmVqM pic.twitter.com/If1TUKkaEZ
— 古書山翡翠 商品情報 (@kosho_yamasemi_) September 4, 2025
(古書山翡翠 商品情報@kosho_yamasemi_さん、アップありがとうございます。)
美の壺 『日本美の再発見』 白川郷 岐阜県大野郡白川村 かまくら 秋田県横手市
タウトは、3年半に渡り、日本に滞在しました。日本各地をめぐり、その様子を日記や写真におさめました。その時の感動が『日本美の再発見』(岩波新書)で知ることができます。
ワタクシがタウトを知ったきっかけです。その本、読みました。農村を訪ねては伝統的なくらしや自然とともにある村の姿に驚嘆したそうです。
特に建築家として眼差しを向けたのが、岐阜県にある「白川郷」でした。
それは、「スイスか、スイスの幻想か」と感動を覚え、合掌造りの家々の美しさ、構造が合理的で論理的だと世界の関心を集めるきっかけとなりました。
白川郷は、世界遺産ですよね。タウトの眼はなんと素晴らしいのでしょう。
また、タウトは秋田の古い街並みが残っていることに喜び、再び訪れた冬に雪のかまくらの情景に心奪われ、「これほど美しいものを見たことがなければ予期もしていなかった。」と語っています。
■じっくり読みたい岩波新書
赤R-10『日本美の再発見』
ブルーノ・タウト 著 篠田英雄 訳
ISBN4-00-400010-6
🔹桂離宮をはじめ、伊勢神宮、飛騨白川の農家および秋田の民家などの美は、ドイツの建築家タウトによって「再発見」された。日本文化の深奥に遊んだ魂の記録。 pic.twitter.com/61aVMl1dEl— オフィスFTIヤマモト (@fti_ymmt) January 10, 2020
(オフィスFTIヤマモト@fti_ymmtさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「理想の暮らしを紡いで」
美の壺 廣瀬 正史(ひろせ せいし)さん 住職 少林山達磨寺 群馬県高崎市
ブルーノ・タウトは、1910年代に鉄やガラスを用いた実験的な作品を発表し世界にその名をとどろかせました。
ベルリンで都市化が進むと住宅不足になり、労働者のために色彩鮮やかな住宅を設計し色彩の建築家と呼ばれました。
しかし、歴史の渦に巻き込まれ、ナチスが台頭するとユートピア思想を持つ社会主義的なタウトは、ドイツを追われ日本へ亡命しました。
日本の大半を過ごしたのが、群馬県高崎市にある「少林山達磨寺」の「洗心亭」とよばれる平屋の建物です。住職の廣瀬正史さんに案内していただきました。
くらしていたのは6畳と4畳半の和室です。伴侶のエリカと2年3ヶ月暮らしていました。囲炉裏があり住んでいた当時がしのばれますね。床の間には「我 日本文化を愛す
ブルーノ・タウト」とあります。洗心亭でのくらしでは、廣瀬さん祖父母が世話をし、伯母も毎朝、2人のために床の間の花を生けていたそうです。
亡命していたタウトは、建築家として活躍する機会は、与えられず、この地で日本文化の著述活動にはげんでいました。
(群馬県高崎市内)久しぶりに
少林山達磨寺へ。
ブルーノ タウト先生が
日本滞在中に住んでた洗心亭の
縁側前へ。
タウト先生が見たであろう
風景を味わってます pic.twitter.com/0yhBBxc89W— 乳井 裕 (@XTBAMss4ABOUZuE) September 7, 2025
(乳井 裕@XTBAMss4ABOUZuEさん、アップありがとうございます。)
美の壺 ブルーノ・タウト 日本暮らしのエピソード
床の間について、タウトは、芸術性や精神性を象徴する空間として絶賛しています。
廣瀬さんは、日本人が、大切にしている場所をタウトも感じていたのだろうと語ります。
洗心亭の建物は、ほとんどが木と紙でつくられています。それは、外気とほとんどかわらない状態で、家の中では火鉢をいくつも置いて、どてらを着こんで生活をしていたそうです。
日本人と同じ格好をして生活感を肌身で感じていたそうです。タウトが日々の日課で欠かさなかったのが散歩でした。集落を見て回り声をかけ地域の人々と交流を重ねました。
昭和10年に起きた水害の時には、当時の50円でバケツを買い、お見舞いとして「水害見舞い ブルーノ・タウト」とバケツに記し、各家へ配布したそうです。
そんなタウトのやさしさに地域の人たちは、とても大切に思い、「タウトさん」、「エリカさん」とさんづけでよんでいたそうです。見舞ったバケツはつい最近まで残っていたそうです。
こんなところにもお互いの心の関係がみえて、すてきなエピソードですね。
高崎市の黄檗宗少林山達磨寺の境内にある(洗心亭)はナチスドイツに睨まれ避難してきたドイツ人建築家 都市計画家 ブルーノ タウト夫妻が生活していた建物です
三国同盟の果てにトルコに亡命したみたいです..黄檗宗総本山は京都の宇治市にありますがお経が歌みたいに聴こえます pic.twitter.com/LT16HskK7G— 井野川三太郎 (@santarou99) April 4, 2025
(井野川三太郎 @santarou99 さん、アップありがとうございます。)
美の壺 マライ・メントラインさん ライター・翻訳家 旧日向家熱海別邸 静岡県熱海市
静岡県熱海市の「旧日向家熱海別邸」は、日本に唯一現存するブルーノ・タウトの建築です。ドイツ生まれで、ライター・翻訳家のマライ・メントラインさんとめぐりました。
マライさんは、13歳から日本語を学び、NHK「テレビでドイツ語」にも出演されていました。旧日向家熱海別邸は、実業家 日向利兵衛の別邸として海を臨む斜面にあります。
タウトは、庭の下にある地下室を設計しました。地下室は、国の重要文化財の指定を受けています。階段をおりると真竹の手すりが出迎えてくれます。曲線の不思議なかたちです。
ヨーロッパで竹はあまりないそうで、マライさんも来日して初めて竹林をみました。
煤竹からつるされた無数に連なる電球は、高さが微妙に違い、波打つようで、ドイツの野外パーティを連想させます。
洋間のワインレッドの壁は、高崎の絹織物にドイツの染料でそめた和紙で裏打ちをしています。タウトの思いが詰まっていますね。日本とドイツのコラボレーションです。
斜面の高低差をいかした階段は、海をながめるためのベンチでもあります。
マライさんは、大きな開口部から見える相模湾を眺め、タウトの作品は、日本で助けてもらった人や日本文化への感謝のあらわれだといいます。
マライさんは、自分とも重ね、建物も書物も同じで、感謝の気持ちを作品に残したかったのだろうと語ってくださいました。
ブルーノ・タウト「旧日向別邸 洋風客間」(1936)
表現主義の建築家タウトが設計した熱海市にある旧日向別邸地下一階。崖上の地形で閉ざされた山側と開かれた海側の間の高低差を階段構造にしたことで舞台上から相模湾の水平線が見える。
〈境界としての半地下〉 pic.twitter.com/hpMZ0LBm1r— フリーデリンデ (@familyparty3) February 3, 2022
(フリーデリンデ@familyparty3さん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「日本の風土をかたちにして」
美の壺 江原 幸太郎さん 学芸員 群馬県立歴史博物館 群馬県高崎市
群馬県立歴史博物館にブルーノ・タウトが、高崎市で手掛けた工芸品があります。学芸員の江原 幸太郎さんに紹介していただきました。
木でできた本のような形をしたものは、伸縮可能な「ブックスタンド」です。意外と大きくなりますね~。ブロックのようにもみえるユーモアなかたちです。
「黒うるしの煙草入れ」は、上から下へとどんどん太くなる線が特徴的です。卵の殻で装飾した小箱や木製のボンボン入れもあります。
タウトは、見る工芸ではなく、見せる工芸の大切さを伝え、身近にある素材の可能性を見出しました。日本で建築の活躍の場がなかったタウトは、300にもおよぶ工芸デザインにたずさわりました。
江原さんは、使わないところも美しくこだわるタウトは、曲線の使い方、見せ方が上手で、古来、日本人が意識していた美意識に共通する所があると言います。
タウトの言葉に「どんな小さなことの中にも全世界を収めることができる」と、あるように有限の中に納まるデザインの中に無限の広がりを見せ、それがタウトの美意識や哲学だと、江原さんは、語ってくださいました。
26日、群馬県立歴史博物館で開催されているブルーノ・タウト展に行ってきました。
タウトデザインの工芸品が展示されています。
このコンパクトに畳める本立て、欲しいです!#ブルーノタウト #群馬県立歴史博物 pic.twitter.com/mFKiYxQVBQ— 今日から東京から来た人 (@xVC2dsFI5cBCU3q) January 28, 2021
(今日から東京から来た人@xVC2dsFI5cBCU3qさん、アップありがとうございます。)
美の壺 前島 美江(まえじま よしえ)さん 西上州竹皮編み伝統工芸士 群馬県高崎市
高崎市にある工房「西上州竹皮編(にしじょうしゅうたけかわあみ)でんえもん」の伝統工芸士 前島美江さんは、ブルーノ・タウトが生んだ工芸の唯一の継承者です。
工房には、タウトがデザインしたワインバスケットや、さいほう箱などが並び、日本生まれでありながら西洋的な雰囲気をかもし出しています。この日、前島さんがつくっていたのは、「パン皿」です。
素材は、タウトの時代と同じ福岡県産カシロダケの竹の皮をつかいます。竹皮を裂き、15本ほどを芯にして竹皮で巻き、たたみ針で縫いこんでいきます。
巻材を固定した縫いこみも模様になって、竹のぬくもりとモダンさがあいまってますね。
高崎市は、雪駄の産地です。日本の職人の技術を高く評価していたタウトが、職人技とドイツのかごあみ技術、自身のデザインを融合させました。
前島さんは、元々、公園を設計するデザイナーでした。40年ほど前、故郷の伝統工芸を守るため竹皮編を継承しました。
なんと素晴らしい。なかなかできないことですね。見えない苦労もあったことでしょう。
タウトの教え子らを訪ね技術を習得し、実物の写真や資料を見ながら、博物館のタウトのデッサンも借用し復元をしました。
前島さんは、日本が持っていた仕組みや地域の資源を活用する力が失われている現在、「もっと人間を大切にしなさい。」と私たちに語りかけているだろうと話してくださいました。
目に見えない大切なものを教えてくれたのがブルーノ・タウトです。
前島美江さん作、ブルーノ・タウトゆかりの西上州竹皮編。 http://t.co/2yVS7tW 福岡県八女市星野村、黒木町、うきは市にしか生えていないカシロダケ(皮白竹)の皮を使って編まれます。 pic.twitter.com/53QlhId
— take_sumi ちくたん (@take_sumi) September 2, 2011
(take_sumi ちくたん@take_sumiさん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。