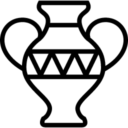こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「じっくり育てる 鉄瓶」。
火鉢に鉄瓶は、似合いますよね~。伝統的な鉄瓶からデザイン的なものまで、じっくり、たっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、アイアンワールドへ。
【来週の #NHKBS #美の壺】は #鉄瓶
東北の風土と手技から生まれた鉄瓶。#大谷翔平 選手も紹介した鉄瓶の製作現場へ!
150年以上使われてきた鉄瓶も登場。
亀が潜む、だるま型、戦前の鉄瓶はまさに「鉄の芸術」#柳宗悦 も共鳴した暮らしの中の「美」#本田明子 #民藝
11日(金)後9時15分 #BS pic.twitter.com/WABY3RyQqt— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) July 7, 2025
目次
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
東北地方に伝わる鉄の芸術、「鉄瓶」の魅力に迫る!▽大谷翔平選手愛用のブルーの鉄瓶・製作現場へ▽1500度の溶かした鉄を扱う職人技!▽4世代が使い込む、料理家・本田明子さん愛用の鉄瓶▽亀が潜み、鶴が舞い、ダルマが睨みをきかせる!多様な戦前の鉄瓶コレクション、その数なんと600!▽民藝運動の担い手・柳宗悦と宮沢賢治ゆかりの民芸店店主が交わした往復書簡▽漆黒の鉄瓶を生む名手の技に密着!<File638>
出典:番組公式ホームページ
【ゲスト】菊地章…南部鉄器工房八代目/小林桜…南部鉄器 職人/本田明子…料理家/堀間重仁…鉄瓶コレクター/菊池翔…弦鍛冶職人/及川陽一郎…民芸品店七代目/佐々木和夫…南部鉄器工房 三代目 草刈正雄(ナビゲーター) 木村多江(語り・天の声)
美の壺:1つめのツボ「変幻自在の生命体」
美の壺 菊地 章さん 南部鉄器工房八代目 岩手県奥州市
1848年創業、岩手県奥州市で8代続く南部鉄器の工房「及富(おいとみ)」が登場します。
工房は、大きな鉄瓶のモニュメントが目印です。現代の鉄瓶は、色や形など多様化が進み、あらゆる世代から支持されています。
昔ながらの漆黒の鉄瓶だけでなく、正方形でかわいい装飾をあしらったもの、前にしか飛ばないことから縁起がいいとされるトンボをモチーフにしたものなど、さまざまです。
人気を集めているのが、末広がりの八角形のフォルムにブルーの色をした商品「みやび」です。
奥州市出身の大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の愛用として紹介され、火がつきました。
ブルーの鉄瓶は、チームカラーとおなじです。ステキな青ですね~。大谷さんは、お湯を沸かしながら故郷に思いをはせているのかしら?
工房代表の菊池章さんにうかがいました。
「みやび」は、30年くらい前にデザインをしたものだそう。
ヨーロッパのお客様からカラフルなものがほしいとの要望で、グリーンやオレンジなどさまざまな色のものを輸出されるようになりました。
近年、日本でもカラフルなものが受け入れられるようになったそうです。歴史あるものづくりを大切にしながら創意工夫をかさね、時代の需要に応えていきました。
みて👀
昨年大谷翔平選手がインスタに投稿した
ブルーの南部鉄瓶
八ヶ月待ってやっと届いたよ✨鉄分補給や整腸作用
デトックスも期待して白湯活はじめます小さめの黒鉄瓶も欲しいな#及富 #南部鉄器 #大谷翔平 #ShoheiOhtani pic.twitter.com/98lapjY4iG
— すい助🌙 右肩インピンジメント&テニス肘 (@kozarun5) January 22, 2025
(すい助🌙 右肩インピンジメント&テニス肘@kozarun5さん、アップありがとうございます。)
美の壺 小林 桜さん 南部鉄器 職人 岩手県奥州市
南部鉄瓶を量産する「鋳込み(いこみ)」の作業をみせていただきました。
鉄は、料理のレシピと同じです。鉄鉱石からとりだした鉄に再利用の鉄を混ぜ理想のかたさを追い求めます。
1.5tもある鉄が、とけ出し、オレンジ色をした液体の湯(ゆ)に変化していきます。菊地さんは、鉄は、金属というより生命体だと言います。
鉄を生き物のように扱います。
湯の色が白くサラサラに変化していくと1400℃を超えています。職人たちは、一斉に動き出し、鋳型に湯を注いでいきます。
そそぐ湯桶は、25㎏もあります。
持つだけでフラフラしそう…。
体力勝負です。注ぐ力加減にも職人技が問われます。
職人の小林桜さんは、鉄瓶や急須は、押し込むように強く入れ、フタなど、うすいものは、強く入れないよう加減をします。
400の砂型に湯が入り、待つこと30分、型をこわすと鉄瓶が、あらわれました。
気温や湿度に左右され難しいそうですが、小林さんは、自分が思い描いているものが出てくると、面白く、だいご味を感じるそうです。
使うことで道具に愛着がわき、大事にしていく、日本人らしい感性が育っていくのだと菊地さんは、語ります。
鉄って生きているんですね。鉄を育てているのが、私たち日本人の心なのです。
本日は南部鉄器工房及富さんとKGR Harmonyさんの工場にお邪魔させて頂きました〜🤩
昔ながらのクラフトとエフェクターの融合。最高じゃないですか!💯❤️@kaito_kiku327 @kgrharmony pic.twitter.com/fNwJeyhap8
— アースクエイカーデバイセス EQD (@EarthquakerJP) May 30, 2024
(アースクエイカーデバイセス EQD@EarthquakerJPさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「先人に思いを馳せる」
美の壺 本田 明子さん 家庭料理家 東京・杉並区
NHK「きょうの料理」や「あさイチ」でおなじみ、家庭料理家の本田明子さんが登場します。
本田さんにとって鉄瓶は欠かせません。朝のマイ行事は、愛用の鉄瓶で湯をわかします。
まぁ~。使い込まれた鉄瓶ですね~。いい味をだしています。
お湯があるとすぐにダシがとれ、野菜もゆでられ、すぐ料理に取り掛かれるそうです。
まずは、湯のみに一杯、冷まして白湯としていただきます。
とがってなくてホッとする味、お茶を入れる時もおいしいそうです。残りは、保温ポットに入れて調理に使います。
本田さんが、鉄瓶を使うようになって3年、母・イセ子さんが亡くなり、遺品整理をした時、目に留まり「使ってあげなきゃ!」と思い持ち帰りました。
幼い頃、体が弱かった本田さんを心配して母は、鉄瓶で湯をわかし、お茶を入れ飲ませてくれました。
この鉄瓶は、元々、お父様が実家の山形から持ってきたものでした。
曽祖父の代から使い150年以上前からあったそうです。
使うたびに本田さんは、今まで何人の手が鉄瓶に触れられてきたのか、亡き人々を思い出すそうです。
道具は生き物で、使った人、作った人、いろんな人の魂が宿っていると感じるそうです。鉄瓶は、ステキに年をかさねています。
本日発売の #クロワッサン 特別編集は「旬の野菜を使い切る、昔ながらのおかず。いつもの野菜編」
旬で安くなった野菜を、昔ながらのホッとするおかずにするレシピをご紹介!
「NHKきょうの料理」「あさイチ」でおなじみの人気料理家 本田明子さんが紹介します✨
お買い求めは書店・コンビニで! pic.twitter.com/xqimUgbdov— マガジンハウス営業部 (@magazine_sales) March 31, 2022
(マガジンハウス営業部@magazine_salesさん、アップありがとうございます。)
美の壺 堀間 重仁(ほりま じゅうじ)さん 鉄瓶コレクター 岩手県盛岡市
南部鉄瓶のもうひとつの産地、岩手県盛岡市は、良質な川砂や鉄が豊富なことから鉄瓶づくりが発展しました。
建設業を営む有限会社堀間組の堀間重仁さんは、45年をかけて鉄瓶を収集しました。
その数、600点、明治時代から昭和初期のものです。堀間さんの収蔵庫には、当時の鋳物師たちが切磋琢磨して技をみがいた鉄瓶がズラリと並んでいます。
すごいコレクションですね~(*_*)
大ぶりの鉄瓶に圧倒されます。
≪駒文羽広形鉄瓶(こまもんはびろがたてつびん)≫は、駒、すなわち馬をモチーフに裾広がりの形をした鉄瓶です。
裾広がりは、熱を逃さない機能を追求しています。
珍しい鉄瓶も紹介してくださいました。明治から大正初期の≪花散磯部に亀文虫喰透し鉄瓶≫は、堀間さんを魅了してやまない作品でようやく手に入れたそうです。
桜舞い散る岩場の影に何匹ものの亀が遊んでいる風景が描かれています。鉄瓶の中には無銘のものも多くあります。
堀間さんを突き動かしたのは、職人たちの卓越した手わざです。
無名の匠による作品が、堀間さんのお眼鏡にかない集いました。
『鐵瓶蒐集控』
約40年に渡って蒐集した鉄瓶の数はおよそ300点。堀間氏の収蔵庫にコレクションされた貴重な鉄瓶を見ることができる大変興味深い図録です。南部鉄瓶を知る上でとても参考になる資料でもあります。engawaにてご覧いただけますので、ご興味のある方はぜひ手に取って見てみてください☺️ pic.twitter.com/iZ6yR0h2MR
— kanakeno (@kanakeno2017) January 27, 2022
(kanakeno@kanakeno2017さん、アップありがとうございます。)
美の壺 菊池 翔さん 弦鍛冶(つるかじ)職人 岩手県盛岡市
堀間さんは、若い芸術家に限り、鉄瓶のコレクションを開放しています。
訪れた人は、全部手に取っていいそうです。採寸をして参考にしてもいいし、貸し出しもしているそうです。
堀間さんは、芸術に理解のある方ですね。いいものは取り入れて、昔のものに負けないいいものをつくるよう励ましています。
素敵だな~(#^^#)。堀間さんは、現代の南部鉄瓶のパトロンですね。
盛岡の伝統文化を残したいと考えているそうです。堀間さんの収蔵庫に通う菊池翔さんは、鉄瓶の取っ手、弦(つる)を専門に作る職人です。
大学で鋳造の技術を学び、弦鍛冶職人の田中二三男さんに師事、盛岡手づくり村に工房「鉉屋(つるや)」を構えています。
現在、盛岡市の弦鍛冶職人は、菊池さんただひとりです。
菊池さんは、古い鉄瓶がつくられた時代、道具の種類もそれほどもない中で、技術の高いものをこれほど多く生み出していたことに敬意を払い、感銘を受けています。
そして、昔、つくったものからもう一歩踏み出せないかと考えています。
昔の人がこんなにいいものをつくったのだから自分も頑張ろうと元気をもらうことも多いそうです。
鉄瓶が師となって現代の芸術家を育てています。
盛岡手づくり村。
今朝泊まったつなぎ温泉は御所湖の対岸にあります。
南部鉄器を作る工程、岩手県の代表的な建築様式「南部曲がり家」が見学できます。 pic.twitter.com/se8Pf939Zi— なかてち🌈🟢 (@nakatechi) March 10, 2024
(なかてち🌈🟢@nakatechiさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「庶民の暮らしの道具」
美の壺 及川 陽一郎さん 民芸品店七代目 岩手県盛岡市
北上川のほとりにある民藝品を集めた店「光原社(こうげんしゃ)」は、大正13年創業。
看板のデザインは芹沢銈介によるものです。光原社は、宮沢賢治ゆかりの地でもあります。
創業者の及川四郎さんは、盛岡高等農林学校の卒業生で宮沢賢治の1年後輩にあたります。
及川四郎さんと宮沢賢治は親交があり、童話集『注文の多い料理店』を出版したのが光原社でした。
ちなみに光原社を命名したのは、宮沢賢治です。光原社の現店主で曽孫にあたる及川陽一郎さんにお話しをうかがいました。
当時、農業の教科書を出版していた四郎さんは、地元に愛情と誇りを持ち、各農学校へ営業に行くときは、必ず手土産に鉄瓶を持っていったそうです。
地元の誇る鉄瓶を自分でもやってみようと考え、昭和2年、鉄瓶の工房を立ち上げました。
光原社は、出版業から鉄器や漆器の製造販売へ移行、民藝運動の父・柳宗悦の目にとまり、交流を深めていきました。
陽一郎さんは、四郎さんが、郷里の生活の中から生まれる鉄瓶が、もっと評価されるべきだという思いが、柳の提唱する庶民から生まれる美と共鳴したのだろうと話してくださいました。
四郎さんがデザインした鉄瓶は、今でもつくり続けているそうです。光原社本店の中庭にある可否館は、クラシカルな雰囲気で喫茶店が併設されています。
民藝作品に囲まれながら、ゆっくり時が流れるのを感じるのもいいですね。
宮沢賢治『注文の多い料理店』を発刊した光原社へ。賢治の書いた原稿が展示されていて、反故紙に何度も推敲が重ねられた『銀河鉄道の夜』は大変興味深かった。撮影禁止が残念。光原社は東北地区の民藝運動の拠点にもなった所で品の良い生活用品を沢山販売している。念願の南部鉄瓶はここで買った✨ pic.twitter.com/Ed1ToD4J3K
— 清水裕子 (@yuko_yuko) October 31, 2024
(清水裕子@yuko_yukoさん、アップありがとうございます。)
美の壺 佐々木 和夫さん 南部鉄器工房 三代目 岩手県盛岡市
盛岡手づくり村にある「薫山(くんざん)工房」では、400年前から伝わる「焼型鋳造法」で鉄瓶がつくられています。
一つの作品をつくるのに120の工程があるそうです。
なんと!多すぎます(*_*)。
工房の三代目 佐々木和夫さんに制作工程をみせていただきました。生地が乾かない間にお手製の真ちゅうのヘラを使い分け、もようを施し細かく表現していきます。
凹凸をつけて模様に深みがでてきました。型にとけた鉄を流し、形ができたらサビ止めをします。工程の中には、盛岡で生まれた技法があります。一説によると、それは、偶然からだったそうです。
鋳物屋が火災になった時、作られた鉄瓶を使わないのは、もったいないと使ったところ、なかなかサビつきませんでした。そして、先人たちが研究を重ね工程のひとつになったそうです。
佐々木さんの工房では、30分ほど900℃の炭火で焼きます。酸化皮膜が生じてサビ止めの効果と鉄臭さをおさえます。
仕上げは、鉄瓶を熱しながら漆を下塗りします。
作っても使ってもらえなければ、ただの鉄、使う人の身になってものづくりをすればいいのかな。と佐々木さんは語ります。
庶民が、使える道具としての基礎を大切に、ものづくりの情熱の火は、消えることなく受け継がれていきます。
おはようございます。
令和4年6月6日(木)
盛岡手づくり村は曇りです。
ちょっと湿度高めです。
最近、南部鉄器の本革焼網プレートがよく売れています!
キャンプ&BBQに向けて準備中の方が多いのかも知れませんね!
#企業公式が地元の天気を言い合う#盛岡手づくり村#くんざん工房#南部鉄器 pic.twitter.com/OxCTKRdVse
— 南部鉄瓶 くんざん工房 (@kunzan_kobo) June 9, 2022
(南部鉄瓶 くんざん工房@kunzan_koboさん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。