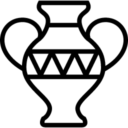こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「今に花咲く 大阪の美」。
大阪といえば食かなぁ?とも思いますがどんな花が咲くのでしょう?…
食文化にも負けない!これぞ大阪の美がたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、ナニワ・the・ワールドへ。
【まもなく! #NHKBS #美の壺 】 #大阪の美
橋にライオンおるんやて!
おぼろ昆布は 堺の刃物の技術が生んだんやて!
箱ずしは 二寸六分の懐石って言われるんやて!
通天閣 には天井画があって 森村泰昌さんが通天閣の前でブリジッド・バルドーやらはってんて!
…知らんけど
よる9時15分 pic.twitter.com/PmDBdjyStp— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) July 18, 2025
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
八百八橋の街、大阪。住吉大社の反橋はなぜ渡りにくい?!▽橋にライオン?大阪市のシンボルマーク?美術史家・橋爪節也さんと大阪橋巡り▽堺の刃物の技術が生んだ「おぼろ昆布」、その濃厚な味わい▽“二寸六分の懐石”と称えられる「箱ずし」の味と彩り▽大阪のシンボルタワー「通天閣」。優美な天井画の復刻秘話!▽ブリジッド・バルドーと通天閣?美術家・森村泰昌さんが語る通天閣への深い思い<File639>
出典:番組公式ホームページ
【出演】橋爪 節也…美術史家 / 神武 磐彦…住吉大社宮司 / 森村 泰昌…美術家 / 西上 雅章…通天閣観光株式会社顧問 / 橋本 卓児…大阪ずし専門店7代目 / 郷田 光伸…昆布商
【出演】草刈 正雄 木村 多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「橋が伝える 街の歩み」
美の壺 神武 磐彦(こうたけ いわひこ)さん 宮司 大阪市住吉区 住吉大社
全国に2300ある住吉神社の総本社が、大阪住吉区にある「住吉大社」です。
大阪では、「すみよっさん」の愛称で呼ばれています。
大阪の初もうでの神社ですよね〜(^^)
神社の創建は、1800年前にさかのぼります。当初は、すぐそばが海で「住吉津(すみのえのつ)」という港が開かれていました。
昔は海だったなんて!意外です。
本殿4棟は、全てが国宝です。
建築様式は、まっすぐ伸びる切妻屋根(きりずまやね)が特徴の「住吉造」です。海の神様をまつっています。
宮司の神武磐彦さんにお話をうかがいました。
奈良・平安時代は、遣唐使の航海安全を願い、江戸時代には、天下の台所としてさかえたそうで、現在も航海安全の祈願にお参りに訪れるそうです。
住吉さんといえば、思い浮かぶのが「反橋(そりはし)」と呼ばれる太鼓橋です。
長さ20m、高さ3.6m、48度の傾斜があり、渡るだけでおはらいになるとも言われています。
神々の通い路としてかけられた太鼓橋ですが、江戸時代になると、人も渡れるようになりました。高い傾斜は、人が渡りにくい橋です。
すごい傾斜ですね。確かに渡るのは少々大変です(- -;)
神様と一緒に渡っていると思うと、より信仰心をかりたてられ、愛されるようになったのだと神武さんは、象徴の太鼓橋のヒミツを語ってくださいました。
「住吉大社」すみよっさん
久し振りの大阪遠征です
全国2300余の住吉神社の総本社で、海の神である三柱の住吉大神と神功皇后を祀る。古代の建築様式を伝える住吉造の四本殿は国宝。淀君奉納の反橋(太鼓橋)は渡るだけでお祓いになる。創建当時の海岸線はすぐ近くにあったそうです pic.twitter.com/8Wf8UMuRkj— は ーいもしもし (@haihainanya) March 25, 2023
(は ーいもしもし@haihainanyaさん、アップありがとうございます。)
美の壺 橋爪 節也(はしづめ せつや)さん 美術史家
高層ビルが立ち並ぶ大阪の街は、かつては堀や川があり多くの船が行き交い、そのなごりが、今も残っています。
大阪は、「八百八橋(はっぴゃくやばし)」とも言われ、たくさんの橋があります。水路が街の原動力となり、天下の台所として発展しました。
大阪の文化・歴史を30年以上、研究している橋爪節也さんと大阪の橋を巡りました。
江戸時代、筑前黒田藩によってかけられたのが「筑前橋」です。
肥後藩の蔵屋敷があったことが名の由来になるのは「肥後橋」、歩行者専用の「錦橋」は、昭和のはじめに土佐堀川にかけられた可動堰(せき)。
橋の下には浄化用の水門があったそうです。
大阪の大動脈御堂筋が通る「淀屋橋」は、豪商の屋号、淀屋さんからきていて自分の屋敷の南と北をつなぐ橋だったそうです。
スケールが大きすぎます!(@@)
面白い書籍を入手。
見開き2ページでお話が完結していて、貴重な図版も多数。
目次がアーチ型になっているのもいいですね。伊藤純=橋爪節也=船越幹央=八木滋『大阪の橋物語』(創元社、2010年) pic.twitter.com/3N0Gwd2SJm
— SAITOH Takuya (@SAITOHTakuya2) January 16, 2024
(SAITOH Takuya@SAITOHTakuya2さん、アップありがとうございます。)
美の壺 難波(なにわ)橋
装飾の美しい橋も紹介していただきました。
「難波橋」は、別名・ライオン橋という名で知られています。江戸時代幕府が管理する公儀橋でした。現在の橋は、大正4年にかけられたものです。
橋には、南と北にそれぞれ2頭、計4頭のライオンの彫刻像があります。一頭は口を開け、もう一方は、口を閉じ「阿吽(あうん)の呼吸」のように立っています。
情緒を感じる橋です。
橋爪さんによると、当時の彫刻は西洋の影響があるそうです。フランス・セーヌ川のアレクサンドル3世橋のライオンを取りこみ、東洋と西洋の融合がうかがえます。
そして、親柱には、大阪市のシンボルマークにも使われているマークがあります。
澪標(みおつくし)からきているもので、港にやってきた船が浅瀬に乗りあげないよう進める標識です。
大阪の繁栄は、昔から水運に負うことが多いという証です。水の都大阪のゆえんですね。
「難波橋」
江戸時代、数多くある橋のなかで特に重要な公儀橋として位置付けられていた浪華三大橋。そのうちのひとつ難波橋は、阿形・吽形2体のライオン像が対で各々橋の南北に鎮座。“ライオン橋”の愛称で親しまれてきた。
細部にまで拘った意匠から、橋がかつて建築土木の花形であったことがわかる。 pic.twitter.com/3uL9hCeJTt— まあくん (@City_Fairlady) January 21, 2024
(まあくん@City_Fairladyさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「技が支える 深き味わい」
美の壺 郷田 光伸(ごうだ みつのぶ)さん 昆布商代表 大阪・堺市
大阪・堺市は、北前船の最終寄港地として栄えた街です。
最盛期には、140軒以上の昆布の店があったそうです。大阪のだし文化を伝える昆布は、産地である北海道や東北から運ばれてきました。
現在も昆布商を営む店が、ちらほらあります。
昆布商「郷田商店」の3代目 郷田光伸さんによると、堺は、刃物の技術があったことから昆布を切ったり、刻んだりした加工が盛んになったそうです。
真昆布を酢漬けにしてやわらかくして刃物で削るおぼろ昆布の作業をみせていただきました。
わぁ〜!勢いよくキレていますね(*^^*)。大阪のうどんには、必ずのってて、いい味を出します。
昆布を削る作業は、結構難しい作業で、包丁も鋭ければ良いというわけでもないそうです。平らな包丁の角度をわずかに曲げることで、キレイなおぼろ昆布ができるそうです。
大阪では、おぼろ昆布をうどんに入れ、残った芯の板状の「白板昆布」は、バッテラなどのさばの押し寿司に使われるそうです。
余すところなく使われているのが、大阪商人の気質なのでしょうか。
これは、大阪に古くから伝わる食文化だそうです。郷田さんは、大阪に根付いた文化を今後も守っていきたいと語ってくださいました。
【 企業紹介 No.10 】株式会社郷田商店(堺市)https://t.co/OfofY23uNG
堺の伝統産業である手すきのおぼろ昆布やとろろ昆布をはじめ、さまざまな昆布製品を取り扱っています。 pic.twitter.com/DGHT7wonvg
— FactorISM(ファクトリズム)〜アトツギたちの文化祭〜 (@FactorISM2020) September 9, 2023
(FactorISM(ファクトリズム)〜アトツギたちの文化祭〜@FactorISM2020さん、アップありがとうございます。)
美の壺 橋本 卓児(はしもと たくじ)さん 大阪ずし専門店店主 大阪市中央区船場
大阪・船場は、古くから大商人が集まり住んでいた地です。
現在でも歴史的建造物が残されています。箱寿司は、船場だからこそ生まれたものだといわれます。
大阪といえば箱寿司や太巻きのイメージがありますよね。具だくさんがうれしい〜(*^^*)
江戸時代の1841年創業、大阪ずし専門店「吉野寿司」の看板商品は、もちろん箱寿司です。
木型で押した「押し寿司」にも種類があり、「箱寿司」は、正方形の木型を使って、いろんな食材をいろどり良く、そして、たくみに組み合わされて作られます。
おいしそうですね\(^o^)/
7代目の橋本卓児さんによると、船場は、昔から裕福な商家が多くあり、食通の方がたくさんいてそのダンナさんたちを喜ばせるためにできたそうです。
3種類のすしを組み合わせます。
直火で香ばしく焼き上げた穴子にシャリをていねいに詰めて、炊き込んだシイタケを混ぜます。木型で押すのは空気を抜いているそうです。
ほ~。ぎゅぎゅっと詰めているのじゃないんですね〜。
すべての食材にたっぷり手間をかけます。
箱寿司は「二寸六部の懐石」と称されるそうで、酢の物や煮物、焼き物という懐石の仕事が二寸六分四方にとじこめられています。
橋本さんは、からだが喜ぶような、食べたらほっとするような味で、派手さはないけれど、キレイで、よくできた寿司だと箱ずしについて語ってくださいました。
江戸とは違う粋(すい)を感じさせてくれます。
大阪 吉野鯗(ずし)
の箱寿司に憧れる
まるで箱庭のようで江戸寿司よりもその歴史は古く
素材ごとの熟練職人がいて
調理している( 拾い画像 メモ ) pic.twitter.com/ryoVzHCsTc
— オボネコ (@obo_neko) May 24, 2019
(オボネコ@obo_nekoさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「人々の心を映す」
美の壺 西上 雅章(にしがみ まさあき)さん 会社役員 大阪市浪速区
大阪・浪速区にある大阪のシンボルタワー「通天閣」は、戦後の昭和31年に建てられた2代目です。
設計は、内藤多仲(ないとうたちゅう)によるものです。
初代は、明治45年に凱旋門の上にエッフェル塔をのせるというアイデアからうまれました。なんとまぁ~。
まー、斬新な案ですね。ミックスしたのが大阪らしい~(^^)
初代通天閣は、一大観光地として人気をはくしたものの昭和18年に火災にあい、撤去されました。
通天閣観光株式会社の顧問 西上雅章さんは、父から初代の通天閣について「天井部分に絵が描かれて、きれいだった。」とよく話を聞かされていたそうです。
父が愛した天井画を復刻したいと考えましたが、残された資料はモノクロの写真だけでした。
その後の調査で、東京に天井画の草稿が残されていたことが判明、描いたのは、版画家の織田一磨によるものでした。
3羽のクジャクが左右対称に楽園に遊ぶ絵でした。
草稿から得られた情報を元に日本画家が原画を制作して復刻されました。色あざやかな花々がクジャクを取り囲んでいます。
父が若い頃、働いていたときの天井画を現代の人にみてもらえて、うれしいと語ってくださいました。
1956年10月28日、通天閣が再建されました。
初代通天閣(写真左)は、1912年に当時「東洋一のタワー」として建築されますが、 1943年に延焼火災で焼失します。
二代目通天閣の設計者は、ほぼ同時期にできた名古屋テレビ塔・東京タワーなどを手がけた内藤多仲で「耐震構造の父」とも呼ばれています。 pic.twitter.com/1eaQPhLhFN— RekiShock(レキショック)@日本史情報発信中 (@Reki_Shock_) October 27, 2024
(RekiShock(レキショック)@日本史情報発信中@Reki_Shock_さん、アップありがとうございます。)
美の壺 森村 泰昌(もりむら やすまさ)さん 美術家 大阪市住之江区北加賀屋
近年、「アートのまち」として注目を集めている住之江区北加賀屋は、かつては造船の街として栄えていました。
その一角に美術家 森村泰昌さんの個人美術館「モリムラ@ミュージアム」があります。
ご自身がゴッホやマリリン・モンローといった芸術家や著名人に扮したセルフポートレートが人気となり、国際的に高い評価をうけています。
森村泰昌さんといえば以前、「しあわせの小宇宙 台所」<File487>にもご出演でした。
美の壺 「しあわせの小宇宙 台所」<File487>お店や場所はドコ?出演者情報もお見逃しなく!NHK美の壺
森村さんの作品の中には、通天閣を背景とした作品があります。
《セルフポートレート(女優)/バルドーとしての私・2》は、往年のフランスの女優、ブリジッド・バルドーにふんした森村さんが、通天閣を背景にうつされています。
通天閣は、初代のエッフェル塔と凱旋門を合体したユニークなデザインで、パリもどきの風景が自分の生まれ故郷の大阪にあるのだと考えました。
「通天閣」と「エッフェル塔」、そして「ブリジッド・バルドー」の3つのモドキがひとつの画におさめられたオリジナルな世界を表現しています。魅惑的な世界だわ~。
つくられたのは、30年ほど前の1995年です。森村さんが、制作当時のエピソードを語ってくださいました。
通天閣のある新世界エリアは、労働者の街、カオスでした。
さまざまな暮らしをしている人がいて、のんだくれのオッチャンやその他、いろんな人がいるところで写真を撮っていたそうです。
「アレはなんだ、男か、女か。」と、ザワザワとした空間で生まれた作品だったそうです。大阪らしい発想の作品ですね(^^)。
美術家の森村泰昌が扮装するレオナルド・ダ・ヴィンチによって解き明かされる歴史上の偉人たちに共通して伝承される “何か” を創造させてくれる仕掛けが味わえるモリムラ@ミュージアム『顔ーKAO』展 ながく一貫してセルフポートレート作品で表現されているので、さらに納得してしまう異様さが面白い。 pic.twitter.com/3Y1Udq4Sm0
— ▱≪3 (@s9uare6usher) January 27, 2023
(▱≪3@s9uare6usherさん、アップありがとうございます。)
美の壺 浄春寺(じょうしゅんじ) 大阪市天王寺区
大阪で生まれ育った森村さんが、自分にとっての通天閣と大阪を感じられる場所を案内していただきました。
訪れたのは、「天王寺七坂」のひとつ、口縄(くちなわ)坂の上にたたずむ「浄春寺」です。
こちらには、森村家のお墓があります。
浄春寺は歴史も古く平安時代の歌人、藤原家隆の菩提所として開かれたと伝えられています。森村さんは、菩提寺の境内からひとりで眺める風景に風情を感じるそうです。
ぽつんとひとりで立つと、通天閣を自分と同じひとりの「通天閣さん」ととらえ、通天閣さんもひとりでたたずんでいると思うそうです。
大阪の街は、表面的には、「おもろい」とか「ド派手」だとか「コテコテ」とか、明るいイメージを連想するのですが、その裏側にある人間の悲しみの色のようなものも、大阪の街は、抱えています。
森村さんは、そんないろんなものを通天閣がひとつにして包み込んでくれるように思えるそうです。夕日に染まる通天閣は、今日も大阪のシンボルであり続けています。
ええ色やね~(^^)
大阪市天王寺区夕陽丘にある「浄春寺」さん。
其の門前に「芭蕉の墓」と「芭蕉反故塚」がありまする。
何れも芭蕉100回忌の1793(寛政5年)に建碑せられたもの。
「浄春寺」さんには、「田能村竹田」「麻田剛立」など江戸時代の文化人の墓が多数ありやんす。 pic.twitter.com/PpojEE0tXa— オヒョウ@2025=漫画534/文字本418 (@griffons_11) December 25, 2016
(オヒョウ@2025=漫画534/文字本418@griffons_11さん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。