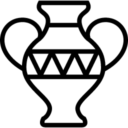こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「日々を楽しくおいしく 小鉢」。
小鉢は、いろんなものが盛れて、幅広いアレンジができますよね~。料理にはえる小鉢がたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、こばちワールドへ。
【明日の #NHKBS #美の壺 】は #小鉢
日本の食卓に欠かせない器「小鉢」の魅力を深堀り。
多種多様な小鉢のデザインは
インバウンドにも大人気。
茶懐石で発展した #割山椒 には日本人ならではの美学が潜む!#藤井恵 #北大路魯山人
25日 後9時15分 #BS pic.twitter.com/H1cAS8URYq— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) July 24, 2025
目次
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
一汁三菜が基本の和食。煮物や酢の物などを盛るのが小鉢。▽小鉢の形は多種多様。丸や四角の他 桔梗に菊などの花の形。平安貴族の木沓(きぐつ)を模した小鉢まで▽料理研究家の藤井恵さんが思い出の小鉢を披露。藤井さんが長年憧れていた小鉢のある暮らしとは?▽江戸時代中頃、小鉢を使う食習慣が広がった理由▽400年前から作られ続ける名小鉢「割山椒」の美<▽北大路魯山人の名器も登場!<File640>
出典:番組公式ホームページ
【出演】内木 雅子…和食器店 店主/神崎 宣武…民俗学者/藤井 恵…料理研究家/管理栄養士/大野 友之…茶懐石の店 店主/荒木 漢一…陶工
草刈正雄 木村多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「食卓に自由な景色を」
美の壺 内木 雅子(うちき まさこ)さん 和食器店 店主 東京・渋谷区
東京・表参道にある和食器店「うつわのみせ 大文字」は、産地や作家にこだわらず、上質なものをとり集めています。
今回の主役「小鉢」の品揃えも豊富です。
四角に丸型、六角形、花や植物をかたどったものもあります。わぁ〜。色鮮やかで日本の伝統模様まで、まるで花が咲いたようですね〜。
外国人のお客様も多く訪れます。
デンマークからグループで観光に来られた方は、和食のお店でさまざまな料理が盛られるのを見て小鉢に興味がわいたそうです。
キレイな色で形もステキだと大喜びです(^^)
店主の内木雅子さんによると、「何に使えばいいのですか?」とよくたずねられるそうですが、小鉢は、必ずこれを盛らなくてはならないというルールはありません。
自由に使っていただければ…。と語ります。
小鉢には自然をモチーフにしたものが多くあります。桔梗や菊のかたちをしたもの、食べているうちに花弁が見えてくるものもあります。
植物の十草(とくさ)から転じた模様の小鉢は、一本一本、表から裏までていねいに絵付けがされています。
平安時代の貴族の木沓(きぐつ)に似た小鉢や透し彫りまで、職人の高い技術が、小さな小鉢に込められているのです。
神宮前にある独身時代から大好きなお店「うつわのみせ・大文字」へ♪25年振りの訪問でした。アレもコレもと欲張りたいところを必死に抑えて、今日はえんどう豆とそら豆の箸置きと片口注器を。市場かごに入れて大事に持って帰りました pic.twitter.com/yxpSy7siPL
— Jinko (@jinko1015) April 17, 2024
(Jinko@jinko1015さん、アップありがとうございます。)
美の壺 神崎 宣武(かんざき のりたけ)さん 民俗学者
民俗学者の神崎宣武さんが登場します。
日本で多種多様な小鉢が、使われるようになったのは、江戸時代のうつわの変化が、大きく関係していると、神崎さんは考えています。
小鉢が受け入れられた理由を教えていただきました。
日本では、古来より木の器を使っていました。
おもてなしの席で使われる漆のうつわは、左に飯碗、右に汁椀があり、向付(むこうづけ)の椀が、おかずを盛る小鉢の役割でした。
漆のうつわは、扱いが難しいものです。使用後は、ていねいに洗い、やわらかい布でふき、乾燥させます。
そして、ひび割れから守るため、布や和紙にくるんで保管します。
手間がかかって大変ですね〜(@@;)
時代が流れ、江戸時代になると磁器が登場します。磁器は、表面が強く、コーティングがされていて水切れも良いのです。
扱いも漆や陶器に比べてもそれほど神経質にならなくてもよく、便利です。
江戸時代の半ばには、磁器の小鉢が庶民の食卓に広がりました。
また、手に持っても不作法とはならないということも小鉢の発展する背景にありました。日本独自の食生活が多様な小鉢を生み出し食卓の風景も変わっていきました。
【新刊見本入庫】神崎宣武『「うつわ」を食らう』(読みなおす日本史)https://t.co/ertlQ26pKD 手に持つ茶碗、とがった箸…。食器・作法にみる日本人の食文化!5/17出荷開始。 pic.twitter.com/l40ozAyzPA
— 吉川弘文館営業部official (@yk_sales) May 12, 2017
(吉川弘文館営業部official@yk_salesさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「集める幸せ 使う幸せ」
美の壺 藤井 恵さん 料理研究家
料理家 藤井恵さんが登場します。
藤井さんは、手間をかけずに栄養もしっかりとれるレシピが好評。SNSや書籍で、さまざまな小鉢をそえた献立を提案しています。
ベストセラー『藤井弁当』は、レシピ本大賞「料理部門」の準大賞を獲得しています。
余談ですが、ワタクシらら子の友人の息子さんは高校3年間、「藤井弁当」を毎日自作していました。尊いわー。
さて、藤井さんの食器棚には、いろんな小鉢がそろっています。
藤井さんのお気に入りは、きゅうりのかたちをした木瓜(もっこう)鉢です。丸い形にアクセントがいいですね(^^)
小さい小鉢は、ちょっとした冷やっこなども盛れて、食卓にさみしさを感じさせません。深い小鉢は、汁があるなしにかかわらず大活躍です。
藤井さんには、想い出の小鉢があります。
料理の仕事を初めてまもない頃、娘さんをおんぶして買った花柄の小鉢です。子育てに、仕事にと奮闘しながら小鉢を集め続け、50種類になりました。
小さい頃は、おままごとが好きで、ちいさいうつわに石や葉っぱや小枝を入れるの好きだった藤井さん。
小鉢を見て楽しむと、心の栄養になると話します。
素朴な小鉢に料理家としての原点が詰まっています。
カヌー犬ブックス8/26更新⑤
「飲める献立―おいしいお酒とおつまみで、おうちでゆったり。」-藤井恵-
季節の野菜たっぷりな春夏秋冬のヘルシー献立、小鉢いっぱいの簡単献立、一年中楽しめる鍋献立など油や脂肪控えめでカロリーを抑えた、おいしくお酒が飲める献立を紹介
→https://t.co/cleFZv5S97 pic.twitter.com/g1x4cpTEUY— 古本 カヌー犬ブックス (@Canoe_Ken) August 26, 2023
(古本 カヌー犬ブックス@Canoe_Kenさん、アップありがとうございます。)
美の壺 藤井 恵さん あこがれの小鉢生活
藤井さん流小鉢の使い方をみせていただきました。
色やかたちが重ならないように折敷(おしき)にならべ、組み合わせを考えます。
折敷(おしき)は、以前の放送回「料理が映える折敷(おしき)」<File524>で取り上げられていました。格がぐっと上がりますよね。
美の壺 「料理が映える折敷(おしき)」<File524>お店や場所はドコ?出演者情報もお見逃しなく!
季節の野菜に赤が少ない時は、器に赤を入れて華やかにします。盛りつける料理は、春巻きやコロッケ、ごくごくシンプルな惣菜ですが小鉢にのせると装いが一新します。
メインデッシュの肉料理は、一口サイズに切り分け小鉢に盛ります。小鉢を使えば冷蔵庫にある残り物がステキな御膳に変身しました。
これでゆっくり日本酒をのみながら夜を過ごすのが藤井さんの楽しみだそうです。それはきっと癒される時間でしょうね(^^)!
藤井さんは、「いつかやりたい!」とあたためた夢があります。
それは、旅館の朝ごはんにあこがれていて、折敷の上にいろんな小鉢に料理がのっているのをやりたかったのです。
小鉢をそろえ、子育てがひと段落した今だからこそできる朝御膳をつくります。
花型の小鉢には温泉卵、落ち着いた色あいの小鉢には、焼き鮭が入っています。
いい感じ~\(^o^)/
発芽玄米のごはんにお味噌汁など6つの小鉢の朝食御膳が完成しました。
いろんなものを少しずついただく、小鉢が暮らしにいろどりを添えています。
週末、料理研究家の藤井恵先生の別荘にお邪魔したら、あまりにも心のこもった素晴らしいごはんの数々をいただいて涙出た。そして3月末なのに雪景色! 明日からの新年度がんばれそう pic.twitter.com/cDh5jgdo8J
— 加藤玲奈 (@Rena_Kato) March 31, 2025
(加藤玲奈@Rena_Katoさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「食卓に花咲く小宇宙」
美の壺 北大路 魯山人(きたおおじ ろさんじん) 小鉢「割山椒(わりざんしょう)」
かたち・色・大きさなどが、自由な小鉢の中で、独特なのが「割山椒(わりざんしょう)」です。
400年前の安土桃山時代、千利休が確立した茶懐石の場で使う小鉢としてつくられたものです。
ふっくらとした丸みに大きく入った3つの切れ込みが、山椒の実がはぜたようすに似ていることから名前の由来があります。
たくさんの実をつける山椒は、子宝を連想させ、縁起の良いうつわでもあります。陶芸家 北大路魯山人も割山椒を好んでつくりました。
ふっくらとした丸みに自然な山椒を思わせるような縁とゆらぎ、料理を盛るとすき間から見え隠れするのは、割山椒ならではの演出です。
あら!うつわから料理が、「こんにちわ~」してますね~。
備前焼の風合いがより存在感をだしていますね。器は、料理の着物だと言った魯山人が、好んだ小鉢が割山椒です。
本日は、星岡茶寮の会報誌に掲載されました『唐津風割山椒向付』をご紹介します。
「割山椒(わりざんしょう)」とは、山椒の実がはじけた形をした器です。
北大路魯山人作 金彩向付割山椒。
切り込みを正面に、旬の食材をより引き立てます。会報誌「星岡」(星岡窯研究所刊)
第四十三号 pic.twitter.com/OHxq9cEhek— 宮島「北大路魯山人美術館」公式 (@RosanjinMuseum) April 24, 2025
(宮島「北大路魯山人美術館」公式@RosanjinMuseumさん、アップありがとうございます。)
美の壺 大野 友之さん 茶懐石店 店主 東京・新宿区
茶懐石は、茶会で客人を食事でもてなします。
東京・四谷にある茶懐石専門の料理店「木挽町大野」の店主・大野智之さんは、料理人でもあり茶人でもあります。
会席料理と異なり、茶懐石は、ご飯、汁もの、向付の順で出されます。
大野さんは、向付に鯛の昆布締めを選びました。盛る器は京都・丹後の作家、浅田尚道さんの割山椒の小鉢です。
それぞれ盛られた小鉢は、実の開き具合が少しずつ違います。
集まったお客さん同士が見比べて、「私のうつわは、こうだ。」「あなたのうつわは、こんなのなのね。」と話しながら花が咲くように楽しみを感じてもらいたい遊び心からです。
あらステキですこと(*^^*)
ピンク色した鯛の透きとおった身を割山椒のうつわがやさしく包みこみ花がさいているようです。
世界観というか小さな宇宙が広がっていて、味を楽しみ、選りすぐりのうつわを楽しむのが茶懐石の醍醐味なんだと語ってくださいました。
茶懐石には、なくてはならない存在が割山椒です。
四谷荒木町 木挽町大野
茶懐石のお店が土日にやってる喫茶営業
東京都心とは思えないゆったりしたお座敷で抹茶とお菓子をたのしめる
お茶碗は自分で選べるのでかっこよい楽焼にしてみた
実はお菓子とお茶で千円くらいからだし、おすすめ(要予約)
むかし銀座にあったから木挽町ってついてるらしい pic.twitter.com/yKk0JHA7ZI— ぬーぃてさみ (@buketaoshai) June 7, 2020
(ぬーぃてさみ@buketaoshaiさん、アップありがとうございます。)
美の壺 荒木 漢一さん 陶工 京都・宇治市
ユニークなかたちの割山椒は、どのようにしてつくられるのでしょうか。
京都・宇治市で親子2代にわたり割山椒を手掛ける、工房「笠取土半窯 荒木陶房」の荒木漢一さんを訪ねました。
名工と呼ばれた父・義隆さんは、制作に飽きたり、行き詰まったりすると、基本に立ち戻って割山椒を焼き、陶工としての自分自身を見つめなおしていたと言います。
義隆さんの割山椒は、釉薬を使わない焼きしめが美しい模様となっています。
漢一さんは、父の技術を受け継ぎながら時代にあった新たな割山椒を模索しています。
へらでくぼみをつける工程は、作家のセンスが問われる部分です。父の見本を見ながらつくりますが、父のものより重なりを重視します。
切れ込みの頂点に小さな穴をあけます。
焼いたときに窯の中で割れるのを防ぐためです。そしていさぎよく切っていきます。勘一さんは、割山椒をつくるのは楽しいといいます。
割山椒は、作家の個性が色こくでます。
漢一さんが作るのは、トルコブルーの釉薬にほんのりとした丸みの中にもシャープさが残った和でも洋でも使いこなせる現代の割山椒です。
洋食器のようで食卓にはえますね~(^o^)
割山椒が生まれて400年、受け継がれながらも進化をとげる小鉢です。
今月の特選は荒木義隆(士半窯)、漢一(小僧窯)親子展になります。シンプルで使いやすい、でも作り手の想いが隅々に行き渡っている。トルコブルーの深い色合いや焼〆の力強い風合は、料理を盛るとその味わいを一層引き立ててくれます。#京都 #清水寺 #京焼 #清水焼 #荒木義隆 #士半窯 #荒木漢一 #小僧窯 pic.twitter.com/Nlx0Xll19j
— 京都清水寺門前 京焼・清水焼 清雅堂陶苑 (@seigadotoen) August 24, 2022
(京都清水寺門前 京焼・清水焼 清雅堂陶苑@seigadotoenさん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。