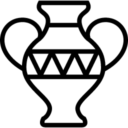こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「京の味 夏」。
京都の夏といえば鱧(はも)。梅肉のそえられた「おとし」や「はもずし」は京都ならではの味覚で大好きです~。夏を代表する食材がたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、京の夏味ワールドへ。
【来週の #NHKBS #美の壺】は#京の味_夏
京都から残暑お見舞いをお届け! #鴨川 の #納涼床(ゆか) で、はもの白身が涼し〜い! #京町家 の台所で、万願寺とうがらしの緑が涼し〜い!老舗の京菓子店で、みずみずしいくずの#生菓子 が涼し〜い! どうぞめしあがれ!
22日(金)後9時15分 #BS pic.twitter.com/EQF8ZG09CE— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) August 15, 2025
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
涼やかに華やかに!京都の夏の美味が登場!▽夏の風物詩・鴨川の「納涼床(ゆか)」。川風をまとう雅な京料理で夢気分!▽貴船の名物「川床(どこ)」では、旬のあゆを風景画のように味わう!?▽京町家の台所に密着!夏野菜のおかずから伝統の漬物まで、暑さを乗り切る旧家のレシピ▽京都人が6月30日に食べる菓子「水無月(みなづき)」に込めた思い▽涼感あふれる京菓子で表現する夏の情景にうっとり…<File641>
出典:番組公式ホームページ
【出演者・キャストほか】
松井 薫…料理店 女将/濱本 晃輔…料理旅館 料理長/秦 めぐみ /石原 義清…和菓子店 店主/髙家 啓太…和菓子店 店主
草刈 正雄(ナビゲーター) 木村 多江(語り・天の声)
美の壺:1つめのツボ「川で味わうなつのひととき」
美の壺 松井 薫(まつい かおる)さん 京料理店女将 鴨川納涼床 京都市下京区
京都の夏は、「油照り」と呼ばれ、盆地特有の暑さで有名です。少しでも暑さを乗りきるため、さまざまな食文化が育まれてきました。
京都の街を南北に流れる鴨川の川沿いの飲食店では、夏の間だけ高床式の座敷が登場します。「鴨川納涼床(かもがわのうりょうゆか)」です。
2025年は5月1日から10月15日までの営業です。店舗によって、朝床営業・昼床営業など営業時間が異なります。川風を感じながら食事を楽しめます。
江戸時代にはすでに鴨川での夕涼みは、にぎわいをみせていたようで、歌川広重の名所絵《京都名所之内・四條河原夕涼》にも描かれています。
創業300余年の料理店「京料理ちもと」の納涼床は、開放的な空間にゆったりとしつらえた座敷、川の音や街のながめ、五感で丸ごと味わえ、夏の特別なひとときを演出します。
女将・松井薫さんが紹介してくださいます。
南座の近くのにぎやかなところに位置するもの鴨川のせせらぎが、あんばいようかき消してくれる、とのこと。
京ことばがステキなおかみさん、暑さを忘れさせてくれるような景色です。京料理ちもとの川床は、1日7組の限定、前日までの要予約制です。
夜は…
「京料理ちもと」さんにて
美味しいお料理で納涼床を堪能
夜風もとても心地よく
最高に贅沢な時間を
過ごさせて頂きました🙌 pic.twitter.com/4sZrkJYTxL— 🩵ma🩵 (@madochan1123) August 30, 2022
(🩵ma🩵@madochan1123さん、アップありがとうございます。)
美の壺 鱧(はも)
日が暮れ、灯りがともりました。
まるで別世界です。うっとり~。絵になりますね。
京料理が、美しい器に盛られ、旬の料理を提供します。その中でも欠かせない食材が「鱧(はも)」です。
生命力が強く海から行きたまま運ばれたはもは、涼しげな白身と上品な旨味が特徴的で、京都の夏を代表する食材として親しまれてきました。
しかし、かたい小骨が無数にあり、食べるのにひと手間が大変です。1ミリほどの間隔に包丁を入れて骨切りをして食べやすくします。
よく見る風景ですよね。コレを見ると夏がきた印象があります(*’▽’)
湯引きをしたハモは、牡丹の花びらが咲いたように身が開きます。京の夏の装いをした八寸は、祇園祭の鉾にみたてた器が、気分を盛りたてます。
料理で華麗な山鉾のにぎやかなお囃子を表現しました。
松井さんは、どのようにしてお客様に旬の料理で京都の遊び心や雅やかさをお伝えできるのか、非日常の空間で京料理を召し上がっていただきながら大人の夏時間を過ごしていただきたいと語ってくださいました。
鱧(はも)
京料理には欠かせないはも。
昔は、暑さが厳しい時期に生きたまま京都へ運べる魚ははもぐらいだったことから大切にされ、京都の夏を代表する魚になりました。祇園祭の間は旬の時期であることから「祭りはも」とも。
みんなでつくる暦情報のWeb図鑑
暦生活(https://t.co/hv9NlcQxdm) pic.twitter.com/GWFfYICBu4— 暦生活 (@543life) July 21, 2020
(暦生活@543lifeさん、アップありがとうございます。)
美の壺 濱本 晃輔(はまもと こうすけ)さん 料理旅館料理長 京都市左京区 貴船
京都市街地より気温が5度程度低いといわれる貴船が登場します。
京都市北部の山間にあり、長年避暑地として親しまれてきました。貴船にも夏ならでは味わいがあります。渓流のすぐ真上で食事を楽しむ「川床(かわどこ)」です。
鴨川は「ゆか」で貴船は「とこ」なんですね〜。見るだけで涼しそう。
川床は、大正時代から続く涼のもてなしで、料理は、川ならではの演出があります。旬の鮎の塩焼きを渓流の景色にのせた「石庭盛り(せきていもり)」です。
料理旅館「貴船ひろや」の料理長 濱本晃輔さんによると、黒漆の盆に石と白砂で風景を描く「盆石」から発想を得たものだと考えられ、盆石をみるなどして勉強をしているそうです。
その腕前をみせていただきました。塩と粒子の細かいコンスターチを使います。大きさの違う粒子が、濃淡を出します。
料理人が画家のように景色を描きます。水鳥の羽根を使ってグラデーションをつけながら白一色で勢いある波を表現します。盃は月に、茶こしは水しぶきの道具として用います。
濱本さんは、目の前の川をみて描いているそうですが、空想の部分もあるそうです。
ナイヤガラでもいいのではと、濱本さんなりの遊び心を添えていただく鮎の塩焼きは一期一会の景色です。
夏の締めくくり。
貴船の川床!
ホンマは夏真っ盛りに来たらいいのだろうけど…混むから9月にしました。
見た目も味も最高!ある意味、芸術!
贅沢なお昼でした。#貴船川床 #貴船 #ひろや pic.twitter.com/H1JAmMAU1e— まる (@maru_to_maru_) September 11, 2024
(まる@maru_to_maru_さん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「巡る季節をいただく」
美の壺 秦 めぐみ(はた めぐみ)さん 京都市下京区 「秦家住宅」
京都のまちに残る木造建築の住まい「町家」におじゃましました。
6月、蔵から夏の建具「簾戸(すど)」が取り出され、ふすまを取り替える作業をします。
畳の上には、ひんやりとした感触の籐(とう)であんだむしろを敷きます。おうちの衣替えですね。こちらも涼しそう~。
この家に暮らす秦めぐみさんは、スイッチが入ると言います。
秦家は、祇園祭の太子山の会所飾りの会場となるため、7月1日の吉符入りまでに夏の仕様にしなければならないそうです。
祇園祭は、京都の街や人の暮らしに生きづいているのですね。
秦さんの家は、明治2年(1869)に建てられた商家特有の表屋造がのこる伝統的な京町家です。
屋根看板には、「奇應丸(きおうがん)」とあり、12代続く小児用丸薬を扱う薬問屋を営んでいました。
現在は、「秦家住宅」として、事前予約制で京町家の暮らしを見学できるほか、1日1組限定で秦家に伝わる家庭料理をいただくことができます。
前祭の山鉾・会所めぐり。そして今回は、太子山の会所を兼ねた築150年の老舗商家「秦家住宅」を訪ねましょう。こちらにお住まいの秦めぐみさんに、祇園祭の行事や、代々守り伝えられてきた京町家の夏の暮らしについて伺います。7/14(日) 抽選受付中☆https://t.co/OpHQk5cuRg pic.twitter.com/Dn5VHRkakS
— 京都ミニツアー「まいまい京都」 (@maimai_kyoto) May 4, 2024
(京都ミニツアー「まいまい京都」@maimai_kyotoさん、アップありがとうございます。)
美の壺 京の夏野菜と漬けもん
秦家の夏支度は、住まいだけではありません。
日々の食事も夏らしくなります。新鮮な夏野菜「朝瓜(あさうり)」が手に入ると必ずつくるものがあります。
「瓜のくずひき」と呼ばれるもので、瓜をあざやかな緑色にゆでて、クズの入ったあついダシとあわせます。秦さんは、夏でも冷たいものを体に入れることは控えているそうです。
見た目は涼しそうな緑ですが、あつい汁でしょうがと梅を添えていただく秦家の定番夏料理です。ほかにもあります。
夏が訪れると作り置く甘酢しょうがは、暑くだるくなると体が求める味です。
地元でとれる万願寺とうがらしは、さっと焼いて、濃口しょうゆでいただきます。台所に立つのも大変な暑いときの強い味方です。
秦家に代々伝わる漬物「ひゃくいち」も紹介いただきました。
乾燥させたナスの葉にぬかと塩でつけた聖護院大根の漬物です。はじめは、きれいな色ですが、気温が上昇するにしたがって塩を打ち調整します。色も茶色のクセの強い味へと変化していきます。
秦さんの母、トキさんは、ひと夏の間に色と味が少しずつ変化していく発酵した漬物を楽しみます。元々、朝は、前日のご飯でおかゆやお茶漬けで短時間で済ませるのが日常でした。
その変化をつけるのが漬物だったそうです。シンプルなのに深みがある野菜が京都の暑い夏を支えているのですね。
「京町家で受け継がれる暮らし 「秦家住宅」の歴史文化に光 来歴が問い掛ける“京都らしさ”」
1/31京都新聞デジタルで、秋元せき・小林丈広・三枝暁子『京都秦家 町家の暮らしと歴史』( https://t.co/gXLGllfEOO )が紹介されました。☞ https://t.co/48GdeX4vfB pic.twitter.com/arqrZ0pckQ
— 岩波書店 (@Iwanamishoten) January 31, 2025
(岩波書店@Iwanamishotenさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「夏を思う」
美の壺 上賀茂神社 京都市北区「夏越の大祓(なごしのおおばらえ)」
京都で最も古い神社のひとつ、上賀茂神社が登場します。
正式名は、「加茂別雷(かもわけいかづち)神社」、広大な敷地の全てがユネスコ世界文化遺産に登録されています。
毎年6月30日に行われる「夏越の大祓」では、半年の災いをはらい、次にきたる半年の無病息災を祈ります。
茅(かや)でできた茅の輪(ちのわ)をくぐると厄がおち、身が清められるいいつたえがあります。
夏の風物詩ですね。ワタクシも毎年、近くの神社の茅の輪をくぐります。
平安時代の和歌には、「水無月の 夏越の祓する人は 千歳の命のぶといふなり」とあるように、夏越の祓いは、千年も昔から大切にされてきた日本の節目でした。
そして、6月30日に食べるのが小麦粉や米粉で作ったういろうの上に甘く煮た小豆を敷きつめたお菓子「水無月」です。
小豆の赤は、邪気を払うといわれています。
水無月は、お店によって微妙に違いますよね。お店に出回る水無月は、店の個性がみられていいですよね。
ワタクシ、水無月の食べ比べをするのがひそかな楽しみです(#^^#)
上賀茂神社で20時から夏越大祓式がありました。式の前にはちょっと塩味のぬるい夏越豆腐をいただき、次に人形に名前を書いて体をなでて息を吹きかけて奉納します。今年は茅の輪くぐりを見ようと待ち構えましたが、見終わったときには橋殿のまわりは人がいっぱいで人形流しはほとんど見れませんでした。 pic.twitter.com/teekBrV3uQ
— ざしきわらこ (@8t7zrNIH0uEKZTG) June 30, 2025
(ざしきわらこ@8t7zrNIH0uEKZTGさん、アップありがとうございます。)
美の壺 石原 義清(いしはら よしきよ)さん 和菓子店店主 京都市上京区 「水無月」
「京菓子司 俵屋吉富」の9代目 石原義清さんに店に残る菓子の図案帖をみせていただきました。貴重なものをありがとうございます。
先々代の祖父・留次郎さんの代につくられた水無月がありました。よく見ると、今のものとは異なり、小豆はパラパラと散りばめられています。
石原さんによると、旧暦の水無月は、現在の6月下旬から8月中旬までの頃で、梅雨が終わり、いよいよ暑くなる夏をむかえる縁起担ぎのようなものだったのだろうと語ります。
本来、水無月は、菓子ではなく、氷室から切りだした氷をさします。平安時代の宮中では、氷室に保存していた氷を暑気払いとして食べる風習がありました。
氷を食べられない庶民は、氷に見立て口にするようになったことが水無月の始まりだと伝えられています。
大事なのは、毎年この時期に水無月を食べることだと、石原さんは言います。
代々、伝わってきたお菓子を食べる習慣や風習を絶やさずに続けることが京都の文化のひとつだと感じているそうです。
店内に水無月を買い求めるお客さまが訪れました。
「暑いので水無月を食べて乗り切ろうと思って」、「季節の仕切りとして食べます。」と口々に話されていました。
京の菓子文化、しつかりと受け継がれていますね。
後輩のモマ氏にDMで水無月をイートインできるとこあったか尋ねてみたら「俵屋吉富さんええんちゃいますか」ということで今出川へ。こちらの本店では併設の和菓子資料館「祥雲軒」で、季節のお菓子とお抹茶をいただくことができる(入館料込み800円)。これは穴場! pic.twitter.com/rV415EBuiM
— ローカル食図鑑 (@kKMGOS77Izd8aBH) June 21, 2025
(ローカル食図鑑@kKMGOS77Izd8aBHさん、アップありがとうございます。)
美の壺 髙家 啓太(たかや けいた)さん 和菓子店 店主 京都市上京区 西陣
京都・西陣で140年以上続く和菓子店「御菓子司 塩芳軒(しおよしけん)」が登場します。
7月、店頭には、水無月に代わる涼やかな菓子が並びます。店主の髙谷啓太さんは、季節にあった京菓子をつくり続けています。
夏、髙家さんがよく使うのが、「葛(くず)」です。
くずを使った生菓子「水牡丹」をつくります。水でとかした葛、砂糖と水あめを火にかけ練り上げます。粘り気がでると透明感が増します。
くずは冷めるとかたくなるため、熱いうちに形をつくります。
熱そうに感じないのですが~。スゴイ手わざですね(≧◇≦)
うすべに色に染めたあんを手早く包みます。ぬれふきんで包んで絞り、氷水へ入れたのち蒸します。くずからうすべに色が透きとおってみえる水牡丹ができました。
髙家さんの水牡丹は、いろいろな夏を表現します。あんの色を緑にかえて初夏の風景を表現しました。続いて、凹凸をつけて金ぱくを散らして、水辺と蛍を表現しました。
あっ!金ぱくが、蛍のあかりですね。
髙家さんは、わからないくらいがちょうどいいのだと話します。何を思うかは、それぞれの思い出の風景や人から聞いた世界など、イマジネーションを広げていただきたいそうです。
それが京菓子の在り方だと、作り手のメッセージを投げかけてくださいました。
おやつに塩芳軒の水牡丹、目に涼しい❄️ #御菓子司 #塩芳軒 #京都 #kyoto #japon https://t.co/srahSsetSF pic.twitter.com/xsdAPFaWKQ
— Helvetica (@Helvetica_) July 23, 2016
(Helvetica@Helvetica_さん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。