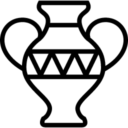こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「沖縄の手仕事」。
沖縄のガラスは存在感があって好きです〜。うつくしい手仕事の魅力がたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、琉球ワールドへ。
強い日差しを受けて光る肉厚なガラスの手。
今回取材した琉球ガラス職人の #松田清春さんが制作しました。#八重山上布、#三線、#琉球ガラス。#沖縄 の美の共演をどうぞ!
後5時30分 #NHKBS pic.twitter.com/BdrFfCzA18
— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) June 11, 2024
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
手仕事の島、沖縄。石垣島の女性たちの手から生まれる極上の布、八重山上布。植物の茎の繊維を糸に、深紅の輝きを秘めたヤマイモが染料に!常に寄り添う影のような存在、三線は島の宝。樹齢500年の黒檀で作る匠の手技とは。唄者、大工哲弘さんが大切にする三線は、愛弟子の形見。ぶ厚く、手なじみの良い琉球ガラスの原料は、泡盛の廃瓶!ガラスに宿る沖縄の精神とは。沖縄、美の共演をご堪能下さい!<File607>
出典:番組公式ホームページ
【ゲスト】平良 佳子…石垣市織物事業協同組合 理事長/浦崎 敏江…石垣市織物事業協同組合員/次呂久 幸子…石垣市織物事業協同組合員/渡慶次 道政…三線 工芸士/大工 哲弘…唄者/上原 徳三…琉球ガラス 工芸士/松田 清春…琉球ガラス 職人
【出演】草刈正雄 木村多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「八重山の授かり物」
美の壺 美の壺 平良 佳子(たいら よしこ)さん 石垣市織物事業協同組合理事長 沖縄県石垣市 八重山上布
沖縄本島から南西に400キロ離れた八重山諸島の石垣島は、海や山に囲まれた自然豊かな地域です。
すみきった青い海、いいですね。癒されます。
自然の産物「八重山上布」は、とんぼの羽にたとえられるほど軽やかな布です。夏着物の代表選手でもあります。
サラサラとした肌ざわりがいいんですよね。
八重山上布のさわやかな風合いの秘密は、糸にあります。島でとれるイラクサ科の「苧麻(ちょま)」の茎の皮からとれた繊維で織られています。
八重山諸島では、500年前から衣服に使われていたそうです。
石垣市織物事業協同組合の理事長、平良佳子さんによると、ちょまは、石垣島では、「ブー」と呼ばれていて、島の女性たちが共同で栽培しています。
時には台風で茎が折れることもあるそうです。
1年を通してちょまの成長を見守り、自然の恵みを大切にいかした布づくりをされているそうです。
ちょまは、収穫して繊維をとり出し、糸をつくって八重山上布へと生まれかわります。
「カラムシ・苧麻」の花。
うちなーぐちでは「ぶー」「まーうー」などと呼ばれる。沖縄では古くから有用植物として利用され、茎から採られた繊維で糸をつくり宮古上布や八重山上布が織られてきた。山羊の好物でもある。子どもの頃葉っぱを服に貼りつけて遊んだあの草です^^ pic.twitter.com/MnEZQ1WBwy— なーはいばい (@jugemax) November 1, 2020
(なーはいばい@jugemaxさん、アップありがとうございます。)
美の壺 浦崎 敏江さん 石垣市織物事業協同組合員
「ブー績(う)み」と呼ばれる糸つくりの作業を浦崎敏江さんにみせていただきました。
根の方は少し太く、上の方は細いそうでうんで抜けないように、つないで、よりをかけて1本にしていきます。
できた糸は緯(ヨコ)糸になるそうです。なんと細いのでしょう。
1着の着物に使うヨコ糸は、12キロメートルも必要なのだそうです。大変な作業ですね。
八重山上布のもうひとつの特徴が、染料です。クール(紅露)と呼ばれる山いもを原料とする染料は、かすり糸に使われる茶色の染料です。
真っ赤な色をしていますが、太陽の光にさらすことで色がかわる不思議な染料だそうです。
山に入りクールをとる作業「クール採り」も島の女性たちが共同で行います。
台風などの影響で、とれない年もあるそうで、今回、4年ぶりのクールとりに密着しました。
山の急斜面をのぼると、まるで宝探しのようです。
協力して分かち合う自然の恵みが八重山上布を支えています。
お取引様のお誘いで石垣島での勉強会。八重山ミンサー、八重山上布が織り継がれています。からむしを育て、糸にして、それを織りあげる。言葉にする事は簡単ですが、布に織りあげる技術は極めて至難そのもの。
米沢も石垣島も全国の産地が先代の技術をつないでおります。#八重山上布#八重山ミンサー pic.twitter.com/nBBt29EZa2— ㈱布四季庵ヨネオリ (@yoneori) October 12, 2023
(㈱布四季庵ヨネオリ@yoneoriさん、アップありがとうございます。)
美の壺 次呂久 幸子(じろく さちこ)さん 石垣市織物事業協同組合員
クールは、2か月間、太陽のもとで濃縮されクール液は、糸を竹の筆で塗りこむ「捺染(なっせん)」技法に使います。かすりの柄の糸になります。
八重山上布のかすりもようは、沖縄のくらしをモチーフにした伝統の柄です。元となるのは、琉球王府が制作した図柄によるもので600種以上もあるそうです。
その昔、琉球王府は八重山の女性たちに布づくりを税として課したため、技術が向上し現在に受け継がれています。
次呂久幸子さんが織る布は、伝統的な柄です。
フシガー(星)にトーニー(物入れ)、トゥイグァー(鳥)を用いて、えさをついばんでいる鳥をイメージしています。
物語になっていてステキですね。
太陽の日に織りあがった布をさらすとかすりの色は濃い茶色へと変化していきます。
そして、干潮の海に6時間さらします。「海ざらし」とよばれるもので八重山上布特有の作業です。
平良さんによると、これは昔ながらの工程。クールは、海にさらすことによって不純物が取り外され、クールの色もちょまの糸もお互いに主張しあうそうです。
平良さんは、「八重山上布を受け継ぎ、次の世代にしっかりと渡さなくてはならない」と語ってくださいました。
美しい布は美しい風景から作り出されます(*´▽`*) RT @yaima_henshubu: きのう行われた、八重山上布の海晒し☆ pic.twitter.com/t934DrnA9J
— 石垣市観光交流協会青年部の人(個人垢) (@isgseinenbu) July 18, 2013
(石垣市観光交流協会青年部の人(個人垢)@isgseinenbuさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「受け継がれる魂」
美の壺 渡慶次 道政(とけし みちまさ)さん 三線工芸士
沖縄の家の守り神といわれる黒檀は、幹の中心がかたく、耐久性に優れています。
「渡慶次三線工房」の渡慶次道政さんは、50年に渡り沖縄の宝「三線(さんしん)」をつくり続けています。
使うのは樹齢500年の黒檀の木片です。樹齢500年!!すごいですね。
総合的にいい三線、沖縄ことばで「美(ちゅ)らかーぎー」をめざしています。複数の道具を使いわけ、時には自身でつくった道具が登場します。
道具は体と一体だと言う渡慶次さん、削りすぎないように金切りノコの刃を束ねて削ります。道具は、手となり指となって直線も曲線も生み出します。
渡慶次さんよると、三線の600年の歴史の中で、黒檀が入手困難な状況だそうです。
渡慶次さんからは、なくなるのはもう決まっていると悲観的な言葉がでますが、黒檀が伝統ではなく、楽器そのものが伝統なのだといいます。
「音楽という文化の灯は、消してはならない、違う木でも美らかーぎーを作るのが私のモットーだ」と、今後も三線を守っていく決意を語ってくださいました。
2024年2月25日付で令和5年度伝統工芸士「三線・総合部門」で当組合より4名の三線職人が登録を受けました。
工芸品名:三線 部門名:総合部門
・渡慶次 道政(渡慶次三線工房)
・仲嶺 盛文(仲嶺三線店)
・譜久山 勝(三線工房響)
・照屋 勝武(照屋勝武三線店) pic.twitter.com/DiW2kZRFeC— 三線組合公式ツイッター (@11sanshin) February 29, 2024
(三線組合公式ツイッター@11sanshinさん、アップありがとうございます。)
美の壺 大工 哲弘(だいく てつひろ)さん 唄者(うたしゃ)
石垣島出身の唄者の大工哲弘さんにとって、三線は唄のお供、身体の一部で友達のような存在です。
大工さん愛用の三線をみせていただきました。
ニシキヘビの皮を張った胴に棹は、沖縄県産の黒檀が使われています。
これぞ、伝統的な沖縄三線ですね。大工さんには、もうひとつ大切にしている三線があります。
チュニジア出身の弟子ブリ・モハメッドさんから受け継いだものです。ブリさんが、おみやげとして持ってきたのもでした。
棹は、チュニジアのオリーブの木、胴は、エイの皮が張られています。
大工さんのもとで三線と唄を学んだブリさんは、才能あふれる青年でした。しかし6年前、訃報の知らせを受けました。
ブリさんの形見の三線を見る度に大工さんは、ブリさんの思う三線を心に焼きつけます。
「自然界を愛する心・言葉を愛する心・人間を愛する心」三つの心で「三心=三線」だと語っていたそうです。
いい言葉ですね。大工さん自身もこの言葉を言い聞かせ唄っているそうです。「三線口説(作詞・大工哲弘)」を唄い亡き弟子に思いをはせます。
ブリさんの人柄を偲ばれるお話ですね。三線の音色がさみしく感じます。
三線組合主催 三線ライブイベントat 札幌
メインプレイヤーは知名定男さん・大工哲弘さん・ #宮沢和史 さん。
それぞれの弟子を代表して、島袋辰也さん・伊藤幸太さん・大城クラウディアさん。
2020年1月25日(土)18:00開演
会 場:共済ホール (北海道札幌市)https://t.co/Y8kyIEnUGD pic.twitter.com/WdnUYrHl1L— みっちゃん♪ (@m_happytogether) October 14, 2019
(みっちゃん♪@m_happytogetherさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「復興のその先へ」
美の壺 上原 徳三さん 琉球ガラス工芸士
沖縄では、明治時代から盛んにガラスづくりがされていました。
しかし、1944年10月10日の沖縄大空襲で島のガラス工場は焼失、終戦直後、アメリカ占領下のもと、廃棄された瓶を原料にグラスがつくられるようになりました。
琉球ガラス工芸士の上原徳三さんは、間近で沖縄のガラス工芸の変遷をみてきました。
上原さんは、15歳で奥原硝子へ見習いとしてガラスの道へ、2019年、「現代の名工」に選出されました。
修業時代には、朝から晩まで空き瓶集めや空き瓶を割る作業のくり返しの日々を過ごしたそうです。上原さんは、生活は苦しく考える余裕もなかったと、当時を語ります。
アメリカ人が廃棄したジュースやビールのびんの色を活かしてガラスを再生させます。
ビンのフタに菊の花もようがあしらわれているお菓子入れは、日本人が買える価格でもなくアメリカ軍などが購入していました。
手厚さやひび、気泡といった再生ガラスの特徴でもある素朴さが、アメリカの人の心に響きました。
手仕事が復興への原動力となって沖縄の人々の自信へとつながっていきました。
上原さんは、「こんな日がくるとは思わなかった、これからもどんどん変わっていく」と沖縄のこれからを語ってくださいました。
ユイカさん、今日は沖縄からの生放送!
沖縄といえば「琉球ガラス」沖縄で100年以上の歴史を持つ工芸品
大戦後の物資不足のさなかでは「廃瓶」を原料としてたくましく再生し、今では沖縄の人々の日用のうつわとしてだけでなく、沖縄土産の定番としても親しまれていますよ
体験もできます
#onej pic.twitter.com/voCnBaX0w9
— ポストウマン (@4KD8NCwzzd5YLyp) March 11, 2023
(ポストウマン@4KD8NCwzzd5YLypさん、アップありがとうございます。)
美の壺 松田 清春さん 琉球ガラス職人 沖縄・中頭郡読谷村
沖縄では、廃ビンを利用したさまざまな琉球ガラスが生まれています。
琉球ガラス職人の松田清春さんは、沖縄が本土に復帰してまもなく琉球ガラスの世界に入り、読谷村に「ガラス工房清天」を設立しました。
こちらの工房では、泡盛の空きビンを使っています。あざやか色のガラスですね。砕いたガラスを1300℃の炉にいれて溶かします。
松田さんは、「廃ビンでも立派にいい商品だと認められたい。」という思いが、今につながっているそうです。
廃ガラスには細かい空気が入りますが、太陽にあてると気泡がキラキラとします。
しかしながら、リサイクルガラス特有の扱いの難しさもあるそうです。
松田さんによると、ガラスは速く冷えて固くなるため、技術を高めることが必要だそうです。
とけたガラスを感覚だけ巻きとり、鉄の棒を組み合わせたモールの型にガラスのたねを入れてひねります。
逆方向にひねると重なり合い、網もようのグラスができました。
空気を入れるタイミングがあわなければできません。松田さんは廃ビンを超える作品をつくりたいと、これからも先をみて進んでいきます。
沖縄県 ガラス工房清天 松田清春
廃瓶を再利用する製法と技法にこだわり、数多くの銘品を生み出し続けている老舗のガラス工房#琉球ガラス #沖縄 #ガラス #グラス #ガラス工房清天 #民藝品 pic.twitter.com/i3pzbh9D08— 暮らしを楽しむ道具たち 季節(とき) (@kurashi_toki) January 16, 2024
(暮らしを楽しむ道具たち 季節(とき)@kurashi_tokiさん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。