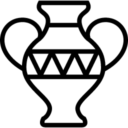こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「いにしえの息吹伝える 琵琶湖」。
琵琶湖は湖というより海かと思うくらいおおきいですよね~。広くて大きい母なる琵琶湖の魅力がたっぷり出てきます♡ 番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、マザーレイクBIWAKOワールドへ。
【明日の #NHKBS #美の壺 】は #いにしえの息吹伝える_琵琶湖
写真家・今森光彦さんイチオシの絶景。春先に見られる不思議な現象「琵琶湖の深呼吸」とは?随筆家・白洲正子が、近江でいちばん美しいと称賛した国宝の十一面観音も!
2日(金) 後9時15分 #BS #BS美の壺は金曜夜にお引越し pic.twitter.com/9zHXXFb5kK— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) April 30, 2025
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
写真家が見守り続ける琵琶湖の極上の景色▽春先に起こる不思議な現象「琵琶湖の深呼吸」とは?▽随筆家・白洲正子が「近江でいちばん美しい」と称賛した国宝の十一面観音の魅力▽湖魚の豊かな食文化▽湖に浮かぶ矢印は、千年前から続く伝統の漁法▽琵琶湖のヨシ原から生まれる「江州よしすだれ」。短いすだれをかけるのは?▽ヨシを何十年も寝かせて生み出す濃淡の美。時をまとって美しくなるすだれの味わい。<File632>
出典:番組公式ホームページ
【出演者・キャストほか】
今森 光彦…写真家/勝見 昌和…漁師/源谷 桂子…料亭女将/関目 正樹…料亭主人/田井中 敏己…すだれ職人/田井中 敏夫…すだれ職人
草刈 正雄 木村 多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「静かなる 時の流れ」
美の壺 今森 光彦さん 写真家 滋賀県大津市
琵琶湖は、滋賀県の面積の6分の1だとか。広いですよね〜。琵琶湖の風景は、多くの人の心をひきつけてきました。大津市生まれの写真家 今森光彦さんが登場します。
今森さんは、子どもの頃から琵琶湖に親しんできました。今森さんが、四季折々のシャッターを切った「仰木の棚田」は、琵琶湖を象徴している場所だそうです。
琵琶湖は、山と湖の距離が近く、水の流れがよくわかるといいます。水が、田んぼや人家を通り抜けて最後に琵琶湖にたどりつきます。水の物語を感じると今森さんは語ります。
冬から春にかけておこる現象があります。「琵琶湖の深呼吸」とよばれる水の循環です。3月初旬、今森さんが狙っている風景です。
日の出前、雪どけ水が山から流れる水が琵琶湖の表面を覆い、湖底の水との寒暖差が生まれます。冷たい水が下へ、湖底の水が上に循環して琵琶湖が深呼吸をするのです。
表面にある水は、酸素をふくみ水の循環がないと困ります。今森さんは、琵琶湖の深呼吸は、とても大事なものだと語ってくださいました。
今森光彦 テレビ出演のお知らせ
NHK ワイルドライフ BSプレミアム
「今森光彦とめぐる琵琶湖 巨大水系に命があふれる」
2020年3月2日(月)午後8時~午後9時 放送 pic.twitter.com/FSIkbhS0Ci— 今森光彦のオーレリアンの庭 (@Aurelian_STAFF) February 25, 2020
(今森光彦のオーレリアンの庭@Aurelian_STAFFさん、アップありがとうございます。)
美の壺 白洲 正子が愛した近江と観音さま 滋賀県長浜市高月
独自の審美眼で日本の文化をみつめてきた随筆家の白洲正子にとって、魅力的な地が「近江」でした。著作の『かくれ里』で、近江は、広く底知れぬ秘密が埋もれていると記しています。
ある時、正子は、琵琶湖北東の湖北地方を訪れました。集落ごとの小さなお堂の中に観音さまは、収められ、村人の手でまつられ、守られています。
随筆『十一面観音巡礼』で、正子は「渡岸寺(向源寺)観音堂」の≪国宝・木造十一面観音菩薩立像≫に注目しています。渡岸寺は、地域の人々から「どうがんじ」と呼ばれ親しまれています。
国宝・木造十一面観音立像は、平安時代の仏像で日本彫刻史上の最高傑作と言われています。ワタクシも渡岸寺の観音さまは、大好きな仏さまです~。美しくてうっとりしますね。
お堂に入ると、観音さまがむき出しの姿で立たれ、装飾は一切なく、供物のみです。正子は、飾り立てるには、観音さまが美しすぎたのだろうと記しています。
右足をわずかに前へ踏み出し、しなやかに腰が曲線を描きます。頭上にはいくつかの仏さまがいます。慈悲深いまなざしの仏さまがある一方で怒りの仏さまもいらっしゃいます。
正子は、険しい表情の仏に目を向け、仏像の作者が悪の表現に重きをおいたのは、作者自身の目で見たもの、体験したものを表現したのだろうと解釈します。
美しい姿の横から邪悪の相がのぞかせ、一番恐ろしい暴悪大笑面は、頭の真後ろにつけ、人間の愚かさを大きな口を開けて笑い飛ばしています。
今日は白洲正子さんの命日。
骨董や能など、日本の美についての随筆を数多く残した。古寺や仏像でも「かくれ里」や「十一面観音巡礼」などで知られている。
正子と次郎夫妻が住んでいた「武相荘」にまた行ってみよう。 pic.twitter.com/PHibUTFFpN— プチトマト (@yfa258134) December 26, 2021
(プチトマト@yfa258134さん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「千年の恵みをいただく」
美の壺 勝見 昌和(かつみ まさかず)さん 漁師 滋賀県野洲市
琵琶湖は、世界有数の古代湖で、誕生は400万年前だといわれています。
琵琶湖の魚のことを「湖魚(こぎょ)」といいます。ビワマスやイサザなど、琵琶湖にしかいない固有種もたくさんいます。
琵琶湖を上空から見ると矢印が浮かんで見えます。魚に入ると書いて「魞(えり)」、魚を誘い獲るための仕掛けです。魞漁は、千年ものの間、琵琶湖に伝わっています。
漁師の勝見昌和さんに同行させていただきました。勝見さんによると、その日、網をあげないと何がかかっているのかわからないのが魞漁だそうです。
水深10m、魞にかかった魚をあげていきます。機械は、使いません。すぐに対応ができる人間の手が一番だそうです。傷がつかないよう、優しくザルですくいます。
アユの稚魚、氷魚(ひお・ひうお)が、かかりました。透き通った可愛いお魚ですね。氷魚と一緒にかかったのは、スジエビとイサザ、そして、ゲンゴロウブナです。
イサザもゲンゴロウブナも琵琶湖の固有魚、湖魚の甘露煮もいいですよね~。勝見さんは、漁師なのでたくさんとれる方がいいのですが、琵琶湖は、限られた水がめなのだといいます。
とりすぎず、自分の体に見合った量がとれるのがいちばんだそうです。琵琶湖の自然と生きている勝見さん、琵琶湖への敬愛、やさしさを感じます。
#Rins通訳案内士
敦賀・長浜 2025年3月 27/35
ちょっと遠出してみました😌魞漁(えりりょう)
琵琶湖をフェリーで巡ると湖面から竹筒のようなものがたくさん突き出ているのを見かけると思います。魚を網の迷路に誘い捕獲する漁法で使われている竹筒で、この漁は魞漁と呼ばれています。 pic.twitter.com/xYlZrgjqPc— リン@英語ラボ (@eiko_eigo) March 9, 2025
(リン@英語ラボ@eiko_eigoさん、アップありがとうございます。)
美の壺 源谷 桂子(げんたに けいこ)さん 料亭女将 村河 克則さん 漁師 滋賀県大津市堅田
琵琶湖の西岸、大津市堅田には、湖上の交通安全を願って建てられた「浮御堂(満月寺)」があります。近江八景のひとつ、「堅田の落雁」でも知られています。
湖畔に100年続く料亭「しづか楼」は、湖の幸を使った伝統料理が受け継がれています。女将の源谷桂子さんに紹介していただきました。
ニゴロブナを塩漬けにしてごはんを重ねた「ふなずし」は、代々、女将が漬けている伝統のお味です。滋賀の食文化を語るには、なくてはならない一品ですね。ワタクシは、酸味が強いのがお好みです。
店の勝手口に漁師の村河克則さんが届けてくれたのは、琵琶湖の固有種「ホンモロコ」です。全長10㎝、銀色の輝きが特徴です。小持ちの出回る2月から4月が一番おいしい時期だそうです。
『湖中産物図証(江戸時代)』には、ホンモロコは、ひなまつりの宴に欠かせない上品でうまい魚と記されています。源谷さんによると、ホンモロコについて、姿は美しく美人、優しく、パワーがあるといいます。
備長炭で火をおこし、ホンモロコが焼かれていきます。「ぴょん、ぴょん…」と跳びはね、ちょっと残酷な気もしますが…。ヒレが透き通り、焼いた魚の頭を網に突き刺します。
脂がのっているので立てると頭がカリっとするそうです。お客様の前で一匹、一匹、焼いてお出しするのは誇らしいことだと語ってくださいました。
紹介された炭火焼で味わう「焼きもろこ」は、要予約で11月~4月上旬まで提供されています。
カメラロールから美味しそうな写真1枚貼るってタグ見て、なんか貼ろうかな〜!って遡ってたらしづか楼の本鴨が出てきて食べてぇ〜〜〜〜〜〜になってる
鴨は美味い。合鴨も美味しいが、本鴨も美味い。 pic.twitter.com/Dn7h0GoATJ— はちえる (@hatieru) December 15, 2022
(はちえる@hatieruさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「空間を装う」
美の壺 関目 正樹(せきめ まさき)さん 料理店主人 滋賀県東近江市五箇荘
水辺に群生する「ヨシ」は、湖を象徴する風景です。ヨシを使った工芸品が近江のくらしに息づいています。琵琶湖の東部、東近江市五箇荘は、近江商人発祥の地です。
現在も蔵や屋敷立ち並び情緒ある街並みです。タイムスリップしたみたいですね。
江戸時代中期の創業で、うなぎ料理や鴨鍋が名物の料理店「納屋孫(なやまご)」の軒下にかけられているのは、琵琶湖のヨシで作られる「江州(ごうしゅう)すだれ」です。
江州すだれは、夏だけではなく一年中かけられています。7代目主人の関目正樹さんにおたずねしました。琵琶湖のヨシをつかったすだれは、近江のシンボルのようなものだそうです。
すだれは、風を通し、日差しをさえぎり、暑さや光をさえぎります。しかし、すだれには、もうひとつの目的があるそうで、庭の景色を引き立てるために掛けています。
影があることで、すだれが額縁のような景色を切り取り、引き立てているそうです。暮らしの中に美しさが、そなわっていますね。風情を感じます。
東近江市に、こんな素敵なお店あるの、知らなかったです❣️
「近江万葉浪漫」の膳
納屋孫は、江戸時代から観音正寺への参拝客や、近江商人本宅へ 料理を提供してきた老舗料理店。復原した近江商人の祝 い膳も提供しています https://t.co/JnzJTukLpL pic.twitter.com/dZBGZ2A4RC— 家持くん@高岡市万葉歴史館(公式) (@manreki) November 14, 2023
(家持くん@高岡市万葉歴史館(公式)@manrekiさん、アップありがとうございます。)
美の壺 田井中 敏巳(たいなか としみ)さん すだれ職人 滋賀県近江八幡市
ヨシの群生地、琵琶湖の東岸に位置する近江八幡市ではヨシの刈り取りが行われています。断ち切って束ねて穂や葉をこそぎ落とします。わずかに機械化されましたがほとんどが今でも手作業です。
大変な作業ですね~。すだれ職人の親子、田井中敏夫さんと田井中敏巳さんは琵琶湖のヨシで「すだれ」をつくっています。3代目の敏巳さんにお話しをうかがいました。
毎年1月から3月にかけてヨシ刈りをします。しないままの状態だと翌年から良いものが生えないらしく、古い芽を刈り取り新芽が育つ環境を整えているそうです。
刈り取ったヨシは、1本、1本、細さや長さを振り分け倉庫へ納めます。およそ200分の1まで選別します。丁寧な仕事ですね〜。倉庫の中には、敏巳さんの祖父が刈り取ったヨシも含まれていて長いものだと30年以上経ったものもあるそうです。
皮がかぶっていないものは、年月が経つにつれて焼け、皮がかぶっているものは本来の色合いで残り、その濃淡を出すために寝かしているそうです。年月が経たないといい味わいが出ないそうです。
ゆっくり、じっくりヨシは生き続けていますね。
7/7(日)のテレビ滋賀プラスワンは「受け継がれてきた逸品」~滋賀県の伝統的工芸品~だwo!
「長村梵鐘」と「江州よしすだれ」が今年新たに指定されたwo!【放送】7/7(日)朝8時30分~ びわ湖放送(BBC)#テレビ滋賀プラスワン #滋賀県 #滋賀県伝統的工芸品 #長村梵鐘 #江州よしすだれ pic.twitter.com/nTxDH34zpW
— うぉーたん(滋賀県公式) (@watan_shiga) July 5, 2019
(うぉーたん(滋賀県公式)@watan_shigaさん、アップありがとうございます。)
美の壺 田井中 敏夫(たいなか としお)さん すだれ職人 滋賀県近江八幡市
敏巳さんの父、田井中敏夫さんにすだれを編む工程を見せていただきました。敏夫さんは、40年連れ添った機械でリズミカルに編んでいきます。1本おきにヨシの向きを変えています。
1本、1本ですか!手が込んでいますね~。ヨシへの愛情を感じちゃいます。敏夫さんによると、ヨシは、株からずっと成長しているそうです。
株の方が太く、先が細いため交互に編みます。節のゆがみを直すため節のところに爪を押し当て修正をしていきます。琵琶湖のヨシは世界一と言われるくらいの強度と光沢を持っているそうです。
敏夫さんは、ずっと後世に伝えられるよう今後も精進していきたいと語ってくださいました。素晴らしい心構え!時をまとって美しくなっていくヨシは、琵琶湖が生んだ伝統工芸です。
田井中さん親子が経営する「株式会社タイナカ」は、90年、琵琶湖のヨシに特化して加工をしてきました。全国の寺社や文化財、民家のヨシの屋根の葺き替えも手掛けています。
琵琶湖の水辺の原風景であるヨシ原。バイオマスの調査が今年もはじまりました。ヨシ刈りをする冬には4m近い高さになりますが、4月はまだ20cmほどの大きさです。かわいらしい赤ちゃんヨシの姿を見ることができるのはこの時期だけ。#琵琶湖博物館 #びわ博 pic.twitter.com/rQeeyeOkc0
— 滋賀県立琵琶湖博物館【公式】 (@biwahaku) April 17, 2025
(滋賀県立琵琶湖博物館【公式】@biwahakuさん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。