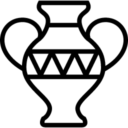こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「風土と技が織りなす 和紙」。
紙すきの所作って、カッコイイです~。暮らしをささえる和紙がたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、ジャパニーズ・ペーパーワールドへ。
【来週の#NHKBS #美の壺】は#和紙 千差万別な和紙の魅力!▽福井・越前の #雲肌麻紙 は横山大観や小杉放庵を魅了▽ #千住博 さんが偶然出会った和紙の力▽日本家屋の障子紙を支えてきた岐阜 #美濃和紙 ▽高知の #土佐典具帖紙 は蜻蛉の羽のような薄さ!▽21日(火)後5時30分 #BS pic.twitter.com/30cMQfj3ym
— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) May 14, 2024
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
和紙は「楮(こうぞ)」や「みつまた」など植物の繊維を原料に伝統的な製法で作られたもの。1300年以上の歴史を持ち、手すきの技術の中には「世界遺産」に登録されているものもある。▽横山大観から千住博まで日本画家の巨匠が愛した和紙▽巨大和紙の製作現場▽長持ちする障子紙の秘密は世界遺産の技術▽自由な模様を楽しむ新感覚の障子紙▽古文書や美術品を和紙で修復▽かげろうの羽のごとく極薄の和紙<File605>
出典:番組公式ホームページ
【ゲスト】千住 博…日本画家/佐々木 美帆…福井県立美術館 学芸員/岩野 麻貴子…岩野平三郎製紙所 四代目当主/加納 武…美濃手すき和紙職人/寺田 幸代…手すき和紙職人/浅場 沙帆…国立公文書館 業務課 修復係/濵田 治…土佐典具帖紙 漉き師/濵田 洋直…土佐典具帖紙 工芸家
【出演】草刈正雄 木村多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「画家を魅了する和紙」
美の壺 千住 博(せんじゅ ひろし)さん 日本画家 長野県軽井沢市 軽井沢千住博美術館
日本画家の千住博さんが登場します。
大画面に流れる滝を表現した《ザ・フォール》を描き、アジア人初のベネチアビエンナーレ名誉賞を受賞しました。
日本画は、板や絹、和紙に描きますが、千住博さんは、比較検討したうえで、「雲肌麻紙」に魅力を感じています。
大学に入って初めて雲肌麻紙を手に取った時、感触がよくて感動したそうです。千住さんによると、大学に入りたての学生は、まだまだ絵の具や紙を使うのは至難のわざです。
うまく使えずグチャグチャになってしまうのですが、雲肌麻紙は、丈夫で破れず、まるで紙が受け入れてくれるかのようだそうです。
ある日、千住さんは、アトリエの片隅にある傷のついた雲肌麻紙から技を見出しました。雲肌麻紙をもみ、シワをつくった上に岩絵具を塗ってがけを描いたのです。
普通の和紙では、破れるか、シワが伸びるのですが、じょうぶな雲肌麻紙は、ゴツゴツとした岩肌の絶景を描きだし傑作とも言える作品を生み出しました。
軽井沢千住博美術館では、1978年から現在までの千住博さんの作品が見ることができます。軽井沢の自然とともに千住さんの描く風景に思いをはせるのもいいですね。
「軽井沢千住博美術館」/西沢立衛建築設計事務所pic.twitter.com/qarMcI76yh
— BOT KENCHIKU🔴 (@BotKenchiku) April 22, 2024
(BOT KENCHIKU🔴@BotKenchikuさん、アップありがとうございます。)
美の壺 佐々木 美帆さん 福井県立美術館学芸員
福井県越前市は、古くから和紙の里として知られている地です。雲肌和紙は越前でつくられています。
やわらかな風合いと厚みがあり、からみ合った繊維が雲を連想させることから名前の由来があります。原料は、楮(こうぞ)と麻です。麻が入ることで強くじょうぶです。
大正末期に雲肌麻紙を考案した岩野平三郎は、「紙すきの神」と称されました。雲肌麻紙が登場すると、多くの日本画家が、驚き、こぞって使ったそうです。
横山大観もその中のひとりです。それまでは絹に描いていました。大観が岩野平三郎にあてた手紙の中には、「今後は、全ての絵を紙に描きたい。」と記しているほど雲肌麻紙にみせられたようです。
福井県立美術館学芸員の佐々木美帆さんは、大観の作品《茄子》からもわかるように、にじませたい所は、しっかりとにじんで、そうでないところはとめられるという、絹ではなかなか表現できない、麻特有のにじみ方を楽しんでいたのだろうと語ってくださいました。
大観は、雲肌麻紙に出会ったことで新しい表現方法を切りひらきました。
竹内栖鳳《晩鴉》(山種美術館蔵)は、墨の濃淡や描法を変えて描き、卓越した表現が魅力の水墨画。本作品には、絵具や墨ののりがよくなるようにと、栖鳳が福井の岩野平三郎製紙所に特注し作らせた「栖鳳紙」が使われているそうです。(山崎) pic.twitter.com/YqJ7xdja
— 山種美術館 (@yamatanemuseum) October 15, 2012
(山種美術館@yamatanemuseumさん、アップありがとうございます。)
美の壺 岩野 麻貴子さん 岩野平三郎製紙所 四代目当主 福井県越前市
岩野平三郎がつくった和紙は、100年たった現在、ひ孫にあたる岩野麻貴子さんに受け継がれています。
岩野麻貴子さんは、株式会社岩野平三郎製紙所の四代目当主として岩野家一子相伝の打ち雲紙・飛雲紙・水玉紙の技法を守っています。
岩野平三郎製紙所は、手すき和紙工房としては日本の中でも最大級の規模です。画家の注文に合わせて大きさや厚さ、こうぞや麻の配合も変えてつくっています。
大きな紙が必要なときは4、5人で紙すきをします。麻貴子さんは、絵画の土台を担う大事な仕事だと語ります。紙は、裏方の存在で作品ができて初めて表舞台に立つことができます。
つくった紙からステキな作品ができると感動するそうです。和紙は、縁の下の力持ちですね。紙がなければ偉大な作品も生まれませんものね。
ホームページのプロフィールによると、麻貴子さんは、ユニクロのヒートテックCMにも出演したことがあると紹介されています。
岩野平三郎製紙所さんにもお邪魔して、見学をさせていただきました
こんなに大きな手漉き和紙が漉ける!
女性が活躍されててとっても素敵でした✨写真はないけど、機械漉きの山伝製紙さんも見学させていただきました
手漉きも機械漉きもそれぞれに良さがあって改めて紙が大好きになりました pic.twitter.com/LytC24RHec
— morikawapaper@盤上遊戯製作所 (@momomopaper) September 8, 2023
(morikawapaper@盤上遊戯製作所@momomopaperさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「匠の技と自然の調和」
美の壺 加納 武さん 美濃手すき和紙職人 岐阜県美濃市
障子紙として有名な美濃和紙は、室町時代の書院づくりの住まいが発達したことから盛んにつくられるようになりました。
うすくて強い和紙で、手すきの技は、重要無形文化財や世界遺産に登録もされています。そして、美濃和紙の中でも品質の高い本美濃和紙です。
手すき職人 加納武さんの手すきの技をみせていただきました。丁寧な手作業です。こうぞをいためないようについているちりを取りのぞくことで、繊維1本1本に光沢ができるそうです。
こうぞをたたいて繊維をほぐしトロロアオイを加え混ぜます。トロロアオイの粘り気が繊維を均一に分散させるそうです。簀桁(すけた)で紙をすきます。
紙をすく時もこうぞのかたまりをていねいに取りはずします。すべて手作業なんてすごいですね。タテへ、横へとすけたを均一に動かし、こうぞを均等に広げます。
加納さんは、こうぞそのものの紙を障子紙に貼ると、日にあたって漂白されて白くなっていくそうです。そして、簡単に破けなく、劣化しないそうです。
紙漉き職人・加納武さんがユネスコ無形文化遺産【本美濃紙】の技を継承する「本美濃紙保存会」の正会員になったとのニュース!喜ばしいですね!!
加納さんは郡上八幡城の来城記念証の和紙も漉いてくれとるんやよ〜!!本当におめでとうございます☆
(^O^)#美濃和紙 #美濃手すき和紙 #御城印 pic.twitter.com/WbQHh7aDzX— およしちゃん (@oyoshi_gujo) June 22, 2019
(およしちゃん@oyoshi_gujoさん、アップありがとうございます。)
美の壺 寺田 幸代(てらだ ゆきよ)さん 手すき和紙職人 岐阜県美濃市
明治から大正時代、美濃は、全国から和紙を売買する人で活気があったそうです。「NIPPONIA美濃商家町」は、大きな紙問屋跡を利用してつくられたホテルです。
客室には、美濃和紙がふんだんに使われています。ホテルの茶室の障子には、このホテルが紙問屋だった頃に扱っていた障子紙の名前が透かしています。
なんて粋なんでしょう。ステキです。この障子紙をつくったのは、手すき和紙職人の寺田幸代さんです。自由な発想で和紙をつくっています。自宅の障子を見せていただきました。
いろんな障子紙がはられてオシャレ感満載です。SDGsかしら‥、こうぞの皮をすいたものや松模様のものもあります。和紙を藍で染めた障子は日の光が入って色の変化を楽しめます。
寺田さんが、7年ぶりに自宅の障子紙を貼り替えます。障子紙にシルクスクリーンで印刷をします。デザインは、藤の花や空に浮かんだ雲など寺田さんがデザインしたものです。
まるで藤の下にいるかのようです。寺田さんは、小さい頃から気に入った紙を集めるのが好きでしたが今は、自分が欲しい紙をつくるのが楽しみだそうです。
朝と夜の光の加減で柄の変化を楽しみます。自然の力は偉大ですね。私たちの暮らしをいろどってくれます。
https://t.co/Wh2SSEs2qx 木の皮から紙をつくる「紙すき職人 寺田 幸代さん」の記事を公開しました。 pic.twitter.com/hYbfcLFsqJ
— あしたね (@ashitane_T) December 6, 2018
(あしたね@ashitaneさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「悠久の命を宿す」
美の壺 浅場 沙帆さん 国立公文書館 修復係 東京・千代田区
東京・千代田区の公文書館は、170万冊の資料が保存されています。古いものは10世紀のはじめのものもあるそうです。本の宝箱のような所ですね。
和紙は、国立公文書館でも活躍しています。劣化や破損した資料の修復にも使われています。業務課修復係の浅場沙帆さんに紹介していただきました。
「つくろい作業」というもので、虫食いのある部分を裏からでんぷんで接着して和紙を貼りつけています。浅場さんによると、和紙は、化学薬品などが入っていないため、経年しても変化が起きにくいそうです。
修復する紙の厚さや色あいからさまざまな紙を使い分けています。器用さを問う作業です。その中でも特別な和紙が、高知県の「典具帖紙(てんぐじょうし)」です。
日本でつくられる和紙の中で最もうすい和紙だといわれています。透けているにもかかわらずなかなか破れません。うすさとじょうぶさを兼ね備えた和紙です。
典具帖紙をはった文書をみせていただくと、表側にはっているのですが文字もはっきり見えて見分けがつきません。
浅場さんは、修復あとが目立つと資料のオリジナル性がそこなわれるため自分の手を加えたあとがわかりにくいときは、いい修復をしたと思うそうです。
国立公文書館では、紙の資料の修復に和紙を用いています。その様子が、NHK BSの番組「美の壺」(エピソード:和紙、本日に初回放送予定)で取り上げられます。是非ご覧ください。https://t.co/vyjxCB4Db4#和紙 #美の壺 #国立公文書館 pic.twitter.com/nNCmpy3YGq
— 国立公文書館 (@JPNatArchives) May 15, 2024
(国立公文書館@JPNatArchivesさん、アップありがとうございます。)
美の壺 濵田 治(はまだ おさむ)さん・濵田 洋直(はまだ なおひろ)さん 土佐典具帖紙 高知県いの町
「土佐典具帖紙」は、高知県いの町でつくられています。その薄さは、カゲロウの羽に例えられます。うすさの秘密は、こうぞの繊維をできるだけ薄くそぐことからです。
土佐典具帖紙は、明治13年、美濃和紙を改良してつくられました。欧米に輸出され、タイプライターの紙として重宝されていたそうです。
最盛期には800人の手すき職人がいましたが、今では濵田治さんと洋直さんの兄弟のみになりました。濵田さん兄弟は、祖父で人間国宝でもあった濵田幸雄(はまださぢお・1931-2016)さんのもとで20年以上、技を学びました。
幸雄さんは、土佐典具帖紙を未来に残そうと奮闘しました。そして、染色の技も取り入れ技術も開発しました。濵田さんの工房では、大ぶりのすけたを使って紙をすきます。
輸出がさかんだった頃、一度にたくさんつくれるように開発しました。勢いよくすけたをふり水をはげしく流すことで繊維をからませます。
伝統を受け継いだ兄弟は、2019年、新しい土佐典具帖紙を作りました。祖父の染めの技術を発展させ光を透過させた薄い和紙です。美しい…和紙じゃないような光沢のある和紙です。
洋直さんは、濵田幸雄は、ただ技を追求するだけの人ではありませんでした。マインドを受け継ぎ昇華させたからこそ今こうして新たな発展ができたのだと語ってくださいました。
高知県 濵田兄弟和紙製作所 濵田洋直
厚さ0.03mmの世界一薄い手漉和紙、土佐典具帖紙。徹底的に不純物を取り除いて漉かれた和紙は、世界中の美術品や古文書などの修復にも使用される。現在この和紙を漉くことが出来るのは、濵田さんだけになった。 pic.twitter.com/tos41IcedV
— Ryosuke Toyama (@ryosuke1080) June 19, 2019
(Ryosuke Toyama@ryosuke1080さん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。