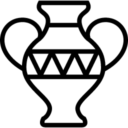こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』スペシャルは、「神社」。
伏見稲荷の千本鳥居もいいですね。朱に塗られた鳥居が別世界に誘ってくれるようです。神社に秘められた「美」がたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、神社詣で。
【「祈りの場」の美しさを】
巫 神 装 祭 建
女 饌 束 り 築
舞…鎮守の森から、国宝の本殿までをたっぷりと。
美の壺スペシャル「神社」
6(金)夜7:30[BSP][BS4K]▼予告動画▼https://t.co/pLKFGD2C6M
▼今年も美しさを▼ pic.twitter.com/18MZmD3vYj
— NHK広報 (@NHK_PR) January 5, 2023
目次
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
ロバート キャンベルさんが大絶賛する大分・宇佐神宮。鎮守の森から、国宝の本殿まで味わい尽くす!▽人類学者・中沢新一さんが日本最古の神社で語る、神社誕生の秘密!▽ド迫力!世界遺産・熊野那智大社の火祭りに密着▽伊勢神宮・出雲大社・春日大社それぞれの建築様式と、写真家の巨匠が福井で捉えた神社建築の美▽平安の伝統を受け継ぐ、神職の装束▽島根の貴重な「巫女(みこ)舞」▽木村多江も念願の奈良・天河神社へ!
出典:番組公式ホームページ
【ゲスト】日本文学研究者 ロバート キャンベル 人類学者 中沢 新一 写真家 藤塚 光政 俳優 安藤 新
【出演】草刈正雄 木村多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つ目のツボ 「思いを託す」
美の壺:ロバート・キャンベルさん 日本文学研究者 大分県 宇佐神宮
近世・日本文学研究者のロバート キャンベルさんは、神社にも造詣が深く九州大学の研究生として調査の合間に宇佐神宮へ訪れたことがあるそうです。
一緒に宇佐神宮を巡ってみました。宇佐神宮は、奈良時代に創建された神社で4万社ある八幡宮の総本宮でもあります。
森が屏風のように覆い、鎮守の森があります。大きな鳥居が迎えてくれました。境内の広さ50万平方メートル、拝礼作法は「二拝四拍手一拝」で三か所を参拝します。
へえ、二礼二拍手一礼/二拝二拍手一拝とは限らないんですね。ワタクシ初めて知りました。
国宝の本殿には「八幡大神(はちまんおおかみ)」、地主神の「比売大神(ひめおおかみ)」、八幡様の母「神功皇后(じんぐうこうごう)」が祀られています。
「八幡造(はちまんづくり)」と呼ばれる建築様式で拝殿、外院、内院と御殿が3つ並び1つの本殿となっています。特別に本殿を拝見させていただきました。
柱や床など全てが朱色です。キャンベルさんによると屋根と屋根が接する形が「M」の形になっていてモダニズム建築の一面もあるそうです。
宇佐神宮は、行きかうの人の匂いや祈り、地表全てを受け入れるような温もりを感じる神社です。
【紫式部の親族ゆかりの地】 宇佐神宮(大分県宇佐市)
御祭神は、八幡大神・比売大神・神功皇后。
紫式部の夫、藤原宣孝は長保元年(999年)末に「宇佐使」となり、宇佐神宮へ下向しています。(翌年2月に帰京) pic.twitter.com/ayqwFdrSwl— 「源氏物語」関連情報bot (@GenjiBot) January 6, 2023
(「源氏物語」関連情報bot@GenjiBotさん、さん、アップありがとうございます。)
美の壺:中沢新一さん 人類学者 奈良県桜井市 大神(おおみわ)神社
奈良県桜井市にある三輪山(みわやま)には、人々の信仰の原型を見ることができます。三輪山は、縄文と弥生の文化が混交して発展していきました。
縄文人は自然が神であり我々人間は神の分身だという考えでしたが、弥生人になると人間と自然と神の間に距離ができ祭祀が必要となってきました。
「大神神社」は、本殿を持たず拝殿のみの神社です。三輪山自体をご神体として祀っていいます。人類学者の中沢新一さんによると、神社の脇道には古い神様が祀られていことが
多いそうです。古い形の神社の祭祀場があり大地の下から何かの力がせせり上がってこの世に姿を現した磐山の姿が「磐座(いわくら)神社」です。
大神神社の背後にある死や闇を山の中で感じとることができた時、古代人に一歩近づけるのだと中沢さんは語ってくださいました。
新年おめでとうございます。遙か4の要所、三輪の大神神社の続きです。拝殿の左手前から、時計回りに三輪山のふもとを進んでゆきます。ゲームに登場した、山体に見立てた磐座(いわくら)を祭る古い形式の摂社があります。QRコードの記された説明版が現代らしさを感じさせます。次に続きます。 pic.twitter.com/r3nixwvgS8
— ネオロマ聖地訪問 (@NeoRomanceFan) January 2, 2023
(ネオロマ聖地訪問@NeoRomanceFanさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つ目のツボ「森羅万象に祈りを捧げる」
美の壺:穂高賢一さん 神職 長野県松本市 穂高神社奥宮
長野県松本市上高地は、日本を代表する山岳リゾートです。登山客や観光客が今日も訪れています。
「上高地」の名の由来は、神が下る地すなわち「神降地(かみこうち)」から由来していると言われています。川沿いの道を歩いていくと鳥居があり、小さな社があります。
標高1500メートルの祈りの場である「穂高神社奥宮」は社殿の裏には穂高岳、山の麓には「明神池(みょうじんいけ)」が広がっています。
江戸時代の資料で明神池は「霊湖(れいこ)」と記されています。神聖な池であることの象徴です。明神池は、山の湧水が溜まった池で寒い冬でも全面凍結はしないそうです。
権禰宜(ごんねぎ)の穂高賢一さんが伝説をお話しくださいました。
2000年前に移り住んだ人が雄大な穂高に感銘を受け、穂高の大神様が降り立ち明神池にも降り立ったそうです。
そういえば昨年も穂高神社奥宮にたどり着き、その次の日に穂高神社を訪問しその事を社務所で伝えると、「ここで遥拝されたら遥拝と書いた奥宮の御朱印を出しますが、そうであれば参拝と書いた奥宮の御朱印を」と対応された。なお、穂高神社はこの時期「三九朗」と呼ばれるどんど焼きが行われている。 pic.twitter.com/k1FU7cRgtu
— どっかいきたい (@shidaeu) January 8, 2023
(どっかいきたい@shidaeuさん、アップありがとうございます。)
美の壺:南 治重(みなみ しげはる)さん、村井 弘和さん 和歌山県熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)
和歌山県南部の熊野那智山(くまのなちさん)にある「那智の大滝」は、古くから信仰の対象となっていました。
熊野那智大社は、滝に祀っていた神様に社殿を設けて移したことからはじまります。
熊野那智大社では、7月「那智の扇祭り」が執り行われます。那智の滝に見立てた12体の扇の神輿に神が乗って里帰りする神事です。
「那智の火祭」とも呼ばれます。その訳を氏子で扇祭り進行役を務める南治重さんが話してくれました。
扇みこしには神様が乗っていらっしゃるので、12本の大たいまつで参道を清めるため火が必要なのだそうです。
大たいまつは、ひのきの板を100本以上束ねて作ります。重さは50Kg、12人の氏子が30分以上担いで参道を歩きます。
氏子の村井弘和さんは、「たいまつを落とさないようにみんなで無事に下ろしたい。」と心境を語ってくださいました。
祭りの終わりには大たいまつの担ぎ手による「那瀑舞(なばくまい)」と呼ばれる舞が奉納されました。古から続く自然への感謝の現れが目に浮かびます。
7月14日、#熊野那智大社 にて #扇祭 が行われます。12基の扇神輿が本社から那智の滝前にある飛瀧神社へ渡御します。重さ50kg以上の12本の大松明の火で迎え清めることから「#那智の火祭」とも呼ばれる勇壮な祭りです。#神社検定 pic.twitter.com/HpGgsVsqqr
— 神社検定⛩️ (@jinjakentei) July 13, 2018
(神社検定⛩️@jinjakenteiさん、アップありがとうございます。)
美の壺:木村多江さん 神社紀行
美の壺:鍵谷将宏(かぎたにまさひろ)さん 組紐工房代表
美の壺スペシャル恒例、木村多江さんの登場です。
まず、木村さんが訪れたのは、京都市中京区二条城近くにある組ひも工房「鍵辨紐房店(かぎべんひもふさてん)」です。
大正3年創業、寺社で使われる飾りひもや房を作っています。
代表の鍵谷将宏さんの母靖子さんに作業を見せていただきました。リズミカルで早い所作です。
この早さ、圧倒されます。そして手の早さとはうらはらに靖子さんの穏やかな表情が印象的です。
今では、ほとんどが機械ですが、鍵谷さんの工房では手くみで作られています。そして、手くみのひもをそのまま使うのではなく結びが施されています。
花を模した菊結びや縁起がよいとされる叶結び、職人さんも難しいという総角(あげまき)結びを教えていただきました。
木村さんもひも結びに挑戦しました。
垂れ下げる布に飾り結びが施されている見帷(みとばり)には、総角結びが8つ並びます。根気が必要な作業です。
思いを込めて作るからこそ、やりがいのある仕事だと鍵谷さんは言います。木村さんは、神社の美の一端を再確認したようです。
ツイ担が紐を打ったら
庵主さんが紐結び。
叶結び、菊結び、総角結び、国結び。こうして不徹寺の訶梨勒は出来上がります。ちなみに香袋も庵主さんが手縫いです。一つ一つ、自分達で。いつか訶梨勒といえば不徹寺!と言われることを夢見つつ。 pic.twitter.com/diio8Rgm8V
— 臨済宗妙心寺派 松壽山不徹寺 (@futetsuji) April 4, 2022
(臨済宗妙心寺派 松壽山不徹寺@futetsujiさん、アップありがとうございます。)
美の壺:柿坂 匡孝(かきさか まさたか)さん 宮司 奈良県吉野郡 天河神社(てんかわじんじゃ)
続いて木村さんが訪れたのは、奈良県吉野郡にある「天河大辨財天神社(てんかわだいべんざいてんじんじゃ)」です。
飛鳥時代より続く由緒ある神社で芸事をする人が多く参拝に訪れます。木村さんも訪れたかったそうで念願が叶いましたね。
宮司の柿坂匡孝さんにお話しをうかがいました。
天河神社は、水の神さまを祀っています。このことから川や水の音、発する音から身体を動かすことにつながり、舞や舞踊という芸事をする人が参拝するようになったそうです。
水は芸能に縁起がいいんですよね。サンズイのつく漢字を芸名にする人もいますよね。
拝殿前には神楽殿があります。神社と能舞台との関係は、室町時代にさかのぼり、世阿弥の息子の観世一郎元雅が能の発展を祈ったことからはじまります。
元雅が寄進した能面を拝見しました。「阿古父尉(あこぶじょう)」と呼ばれる上品な男性老人の面です。
本物に忠実にならった、写しの作品も拝見しました。
このような優れた写しがあるからこそ、能面の伝統が守られてきました。木村さんも神楽殿に立たせていただき、感動されたご様子です。
天河神社と本殿の能舞台 pic.twitter.com/8x7mKJVlN1
— みゅげ (@muguet1230) November 17, 2019
(みゅげ@muguet1230さん、アップありがとうございます。)
美の壺:3つ目のツボ 「時を越えて息づく」
美の壺:藤塚 光政(ふじつかみつまさ)さん 写真家 大瀧神社 福井県越前市
伊勢神宮、出雲大社、春日大社は、日本を代表する神社でそれぞれに個性があり建築方法もさまざまです。
伊勢神宮内宮・外宮の正殿は、「唯一神明造(ゆいつしんめいづくり)」と呼ばれる特別な神明造です。
出雲大社本殿は、出雲地方で特徴的な「大社造」で作られています。
春日大社は、正面に大きく庇(ひさし)が突き出す大きな屋根を持った「春日造」です。
そんな神社など日本の木造建築にこだわり撮影をし続ける写真家がいます。
藤塚光政(ふじつかみつまさ)さんは、安藤忠雄さんや隈研吾さんなど大建築家から信頼を受けている人物です。
今回、藤塚さんが撮影する神社は、福井県越前市にある大瀧神社(おおたきじんじゃ)です。
6世紀末に創建された紙づくりの神さまです。この地域は、越前和紙で有名です。屋根が滝のように幾重にも連なり彫刻が施され重厚感があります。
藤塚さんによると、建物について、どういう発想で建てられたのか?ど思いをめぐらせるそうです。
水が豊富な地域から滝つぼの波をイメージしたのではと藤塚さんは持論を語ってくださいました。
明日のNHK美の壺 スペシャル(90分拡大版)は神社です。
福井県越前市の紙祖神 岡太神社・大瀧神社は僕も好きな神社のひとつで、一昨年のGO FOR KOGEIではここの境内に桑田卓郎さんの作品が屋外展示されました。https://t.co/kOdbNEjyPg pic.twitter.com/cNDTZ16UsY— Joiner®︎ (@nakatateguten) January 5, 2023
(Joiner®︎@nakatategutenさん、アップありがとうございます。)
美の壺:藤井 秀俊さん、久世 隆さん、梶岡 慶子さん 神職の装束 狩衣(かりぎぬ)
神職の装束「狩衣(かりぎぬ)」は、平安時代の貴族の男性がまとっていた衣装です。貴族の日常着として鷹狩りなどに使われていました。
薄い生地に立体的な文様、楕円形の首元が特徴的で平安時代の伝統にならって工程ごとに分業して作られています。
「生地作り」は、シャトル織機で織ります。よこ糸は水に浸した絹糸を用います。藤井秀俊さんによると濡れた糸を使うことで生地がパリッとするそうです。
文様にも秘密があります。左右対称の文様柄をわずかに崩すことでより整った形になるそうです。次の工程は「張り」の作業です。
竹ひごでできた伸子(しんし)で生地を伸ばして刷毛をあてます。久世隆さんは、装束は、「強装束(こわしょうぞく)」といって堅く仕上げるのが基本だそうです。
生地ができると「仕立て」の作業です。生地を重ねて縫っていきます。梶岡慶子さんは、この道7年のキャリアです。
難しいのは首回りの部分です。力がいる作業です。
梶岡さんは、神社にお願いをして昔のものを見せてもらったりして絶えず研究をされているそうです。ここに平安の伝統の形が今も受け継がれています。
毎度おおきに、ありがとうございます。
好天が続き、皆既月食も観測できた京都・下鴨、おかげ様で多忙な毎日です。#装束#狩衣 pic.twitter.com/hb1kDbkXbo— 装束師・はお (@haoshouzokuten) November 9, 2022
(装束師・はお@haoshouzokutenさん、アップありがとうございます。)
美の壺:4つ目のツボ 「つなぐ心」
美の壺:上杉 征子さん 談山(だんざん)神社 奈良県桜井市
奈良県桜井市多武峰(とうのみね)にある談山神社は701年創建。藤原鎌足の長男が遺骨の一部をこの地に移し神殿を作ったことからはじまります。
毎年10月、藤原鎌足に感謝して秋の実りをお供えする「嘉吉祭(かきつさい)」が執り行われます。祭りが近づくと地元の人や神社の人が集い神饌づくりを行います。
みょうがの葉を束ねて芯を作り野菜や果物など秋の恵みを差します。野菜や果物の他、米の神饌もあります。
バリなどの南国を思わせるようなデザインのようにワタクシ思います。
氏子の上杉征子さんは、3000粒の米を幾何学文様にしながら積み上げます。色もカラフルで華やかです。上杉さんは、米御供を20年以上作っています。
平らに積むのは至難の業です。米粒を一周積むのに25分かかります。積み上げた米御供の上にもち米をのせ完成です。
家々によって違いますが見た目をきれいにおいしく飾り鎌足さんにお供えをします。祭りの当日、地域の人の手で作った神饌は神職の手に渡り神殿へと運ばれます。
代々、地域に継承された姿です。
談山神社、今日は嘉吉祭という御祭神の鎌足公に神饌を捧げるお祭り。準備の最中、神饌を間近に拝見することができた。 pic.twitter.com/RxVhyn36Np
— 鳥居 (@shinmeitorii1) October 9, 2022
(鳥居@shinmeitorii1さん、アップありがとうございます。)
美の壺:横山 直正さん 濱地 良佳(はまち よか)さん 神職 美保神社(みほじんじゃ) 島根県松江市
島根県松江市美保関(みほのせき)は、港町で小泉八雲(こいずみやくも)や島崎藤村(しまざきとうそん)が愛した地でもあります。
美保関にある美保神社は、えびす様の総本宮です。1日2回、朝と夕に神事が執り行われます。
祝詞を述べ巫女による巫女舞の奉納をします。舞の所作は秘伝で代々受け継がれてきました。
権禰宜の横山直正さんは、美保神社には「巫女舞」は欠かせないものだと言います。
江戸時代には、巫女を専属とする「巫女家(みこけ)」が5家あったそうです。現在、巫女はなり手が少ない現状ですが、可能な限り伝承を続けたいと語ってくださいました。
巫女の濱地良佳さんにお話しを聞くことができました。濱地さんは、高校生の時、祈りを本職とする生き方を知ったそうです。
舞っている時は、感謝の気持ちが湧きあがってくるそうです。人々の思いや願い、祈りを込めて舞います。これからも受け継いでいきたい伝統です。
この今朝のハイライト。美保神社の巫女舞。恵比寿の総本山という由緒ある立派な神社の、神事が見られて感動。 pic.twitter.com/AGa0UZIX5T
— うえいぶ@メロンブックス委託中 (@ranpo0216) May 1, 2018
(うえいぶ@メロンブックス委託中@ranpo0216さん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。
美の壺・放送予定。再放送はいつ? NHKオンデマンド登録で見逃し視聴もできます。
今回の『美の壺』初回放送は2023年1月6日(金)でした。番組内容もこの時点のものです。
放送スケジュールは2022年4月現在で、
Eテレ「美の壺・選」の放送は、日曜日午後11時~、再放送は毎週木曜日午前11時~です。
過去の放送分から毎週金曜日午後0時30分〜午後1時からと毎週水曜日午前5時30分~です。
BS4Kは、BSプレミアムと同じ毎週金曜 午後7時30分で、再放送は回数が増えて、
土曜日午前6時45分、金曜日午後0時30分、木曜日午後11時30分~の3回あります。
キレイな画質のBS4Kは美の壺のような番組にはピッタリですね!
NHKオンデマンドなら月額の見逃し見放題パックや単品視聴ができます。月々500~600本の番組が放送当日または翌日から見られます。