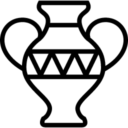こんにちは~。らら子です。
今回のNHK 『美の壺』は、「江戸のおしゃれ」。
かんざしや髪飾り…根付もかわいくていいですよね~。粋でいなせなツボがたっぷり出てきます♡
番組で紹介されたスポットやお店をご紹介。
いざ、江戸っ子ワールドへ。
NHK BS 01/28 17:30 美の壺「江戸のおしゃれ」 #nhkbs #tsubo #美の壺 https://t.co/ZLLNc5kLVw
— NHK BS (@NHK_BS1) January 28, 2025
目次
美の壺:放送内容、出演者情報
【番組予告】
昨年、落語協会では12年ぶり16人抜きで真打に昇進した落語家・三遊亭わん丈さん。こだわりの下駄(げた)を大公開!▽鼻緒だけでも1000種類以上!老舗履物屋で、三遊亭わん丈の下駄(げた)選びに密着!▽歌舞伎などの日本髪を結い続けてきた床山。「死んでも棺おけに入れない」というつげぐしとは?!▽親子3代で使われるという、つげ櫛の驚くべき技▽合切袋などの袋物に見る江戸のエスプリ!<File626>
出典:番組公式ホームページ
【ゲスト】三遊亭 わん丈…落語家 榎本 英臣…和装履物店店主 鴨治 欽吾…床山 竹内 敬一…つげ櫛店店主 木戸 一江…袋物博物館館長 髙林 晋…職人
【出演】草刈正雄 木村多江(語り・ナレーション)
美の壺:1つめのツボ「江戸風情を味わう」
美の壺 三遊亭 わん丈 さん 落語家
落語家の三遊亭わん丈さんが登場します。
令和6年、落語協会では、12年ぶりの16人抜きで真打ち昇進した若手実力派です。滋賀県大津市出身。滋賀県では、初の江戸落語家の誕生です!
三遊亭わん丈さんは古典から新作まで幅広く演じます。
バンドマンでもあったわん丈さん、いつ見てもステキな着こなしをされますね~。わん丈さんの江戸のオシャレをみせていただきました。
着物は、江戸で流行った縞もようの着物「川越の唐桟(とうざん)」に、下駄は、裸足で履いても跡が残らないような色の濃い烏表(からすおもて)。
粋な細めの鼻緒は、帯のハギレをすげたものです。
足袋は、若手時代の手ぬぐいを足袋に仕立てました。犬の足跡がモチーフです。わん丈さん流のこだわりがみられますね。
続いて愛用の下駄を紹介いただきました。
わん丈さんのデビュー下駄は、「糸春雨」といった赤い塗りに黒い線があるものです。黒い斑点のある「ごま竹」は、ゆかたなど夏場に活躍します。
ザラザラ感が素足にあたると気持ちがいいそうです。
高座に上がると履物は見えませんが、見えないところに気を配るんですね。江戸のおしゃれは、足元からですね。
わん丈さんは、
粋であることは、素敵だが、日常に着物を着る人が粋だと言い過ぎると、これから着物でデビューする人がしりごみしてしまい、逆に野暮だと感じる
と語ってくださいました。
滋賀県立美術館でも4月から落語とからめた展覧会をするんですが、町田の文学館ではこんな展覧会が。アドバイザーは柳亭小痴楽師匠。ちなみに尼崎では桂米朝師匠を紹介する展覧会も2月から始まります。滋賀県の展覧会の落語部分の監修は、滋賀県出身の三遊亭わん丈師匠です。 pic.twitter.com/U6G7cQvJXl
— kenjiro hosaka (@kenjirohosaka) January 21, 2025
(kenjiro hosaka@kenjirohosakaさん、アップありがとうございます。)
美の壺 榎本 英臣(えのもと ひでおみ)さん 和装履物店店主 東京・北品川
東海道第一の宿場、北品川にある「丸屋履物店」は、創業、慶応元年、160年前から続く老舗です。
品川宿に店を構えた頃から同じスタイルで、お客様に台と鼻緒を選んでもらいその場ですげます。
店内には、さまざまな色やかたち、素材の台があります。
い草や塗り、鎌倉彫りのものまであるのですね。かたちも丸みのあるものだけじゃないんですね。長方形も新鮮!
6代目の店主、榎本英臣さんによると、「京の着倒れ」「大阪の食い倒れ」に対し、江戸は、「履き倒れ」だそうです。
鼻緒は、店先で職人が1本1本作っています。これも江戸時代からの伝統だそうです。
店内には1000種類以上の鼻緒があります。小紋や、縞、紬や西陣織、印伝、ヨーロッパの素材まで種類は、さまざまです。
選ぶのも悩みますね。
榎本さんは、人とちがったものを着たい、履きたいというのが江戸の美の感覚だそうです。ワタクシもつくってみようかしら。
慶応元年創業の北品川の丸屋履物店さん。
台と鼻緒を選んで足に合わせて目の前ですげて貰えます。
レトロな外観、職人気質なお父さんと可愛らしいお母さん爽やか息子さんの素敵な店でした。
色々教えて頂けて楽しかった!
ありがとうございます。#下駄 #カメラ初心者 #ファインダー越しの私の世界ᅠ pic.twitter.com/o8HIjYo0Ct— なめろう君 (@sapudon) August 13, 2019
(なめろう君@sapudonさん、アップありがとうございます。)
わん丈師匠の下駄のおあつらえに密着
三遊亭わん丈さんが、下駄をあつらえに「丸屋履物店」へ訪れました。どんな下駄になるのでしょうか。
まず、台選びからはじまります。ワクワク感がとまりません。
3つの下駄が最終候補に選ばれました。
長方形の形の「糸春雨」に歯が2枚の下駄、色の濃さの違う竹の皮を交互に織った縞もように「右近」のかたちの下駄と、和紙を織った「しころ」の表に歯がななめになっている「のめり」のかたちの3つです。
のめりは「千両」とも呼ばれ、千両役者が好んで履いていたことから名の由来があります。悩んだ末、わん丈さんが選んだのは、しころの台にのめりの形の下駄を選びました。
鼻緒は、ふすべ(くすべ)という鹿の革をいぶしたものです。
鼻緒からほんのり香りがします。さあ、いよいよすげてもらいます。鼻緒の締め加減は、少々きつめにしました。
のめりの下駄は、初めてのわん丈さん。歩きやすいかたちで、鼻緒の締まった感じもいいと大満足です。
新しいお気に入りの下駄ができあがりました。
その場ですげてそのまま履いて帰れるのも粋な感じがします。
今週も無事終了♪
ご来店頂いた方、Xご覧下さった方、いいね、フォローしてくださった方、ありがとうございました♪明日は定休日です
来週は通常営業の予定です朝5時から藁草履を仕込んでた6代目の写真
朝からうるさかったけど、楽しそうなので、良きです❤︎ pic.twitter.com/YuV7WXD5OZ— 若女将@丸屋履物店 (@maruyanookami) February 1, 2025
(若女将@丸屋履物店@maruyanookamiさん、アップありがとうございます。)
美の壺:2つめのツボ「日本髪を支えて」
美の壺 鴨治 欽吾(かもじ きんご) さん 床山 東京・日本橋
東京日本橋にある「東京鴨治床山(とうきょうかもじとこやま)株式会社」。
歌舞伎や日舞、時代劇に使う「かつら」を数多く手がけています。
江戸時代の女性たちが髪に刺した「かざり櫛」は、貝をもちいた螺鈿(らでん)や天然の素材をいかしたものなど、さまざまな素材や細工で美しさを競っていました。
東京鴨治床山には、1000以上のかざりぐしがあります。
演目や役柄に合わせてつくられているものです。会長の鴨治欽吾さんは、この道70年、立役(たちやく)という男役のかつらが得意な床山です。
1000種以上あるかつらを結いあげるのに使い分けるのが「つげ櫛」です。鴨治さんは、ずっと、つげ櫛しか使っていないそうです。
鴨治さんが、父から受け継いだつげ櫛をみせていただきました。あめ色でつやつやとしています。この櫛、じつは鴨治さんの父が先輩から受け継いだ自慢のくしだそうです。
年季が入ってますね。櫛がこんなに長持ちするなんて!
鴨治さんが「エース」と呼ぶ結いぐしは、さまざまな用途で活躍します。
また、兄からもらった左右が歯の間隔がちがう「ハケコキ」という櫛は、巧みに使いわけます。鴨治さんは、死んでも棺には入れて欲しくない、誰かに使ってほしい櫛なんだそうです。
ワタクシらら子も賛成です!長く使い続けていただきたいですね。
踊りの会では衣裳や挿物の交換が多く、また演目の順番によっては極端に短い時間での作業になることもあるのですが、衣裳さん、床山さんが素早く無駄のないプロの技を見せてくださります。
衣裳:松竹衣裳株式会社
協力:東京鴨治床山株式会社
(撮影:松尾香龍さん)#浅草おどり pic.twitter.com/cJBvde2Pa7— 浅草おどり (@asakusaodori) September 22, 2022
(浅草おどり@asakusaodoriさん、アップありがとうございます。)
美の壺 竹内 敬一 さん つげ櫛製造販売店店主 東京・上野
東京・不忍の池にある「十三や(じゅうさんや)」は、300年ほど前、元文元年創業のつげ櫛専門店です。
店内には鹿児島県産のつげにこだわった櫛がならびます。
江戸時代から続くスタイルで店先でひとつひとつつくられています。15代目の竹内敬一さんによると、親子三代で使われている方もいるそうです。
だからこそ恥ずかしい仕事はできないそうです。江戸っ子ですね~。
店の前には乾燥しているつげの木があります。生木だと使えないため芯まで乾かすのに5年かかるそうです。そこから60工程をかけて1本のくしをつくります。
長い道のりですこと!
使う道具は、江戸時代からほとんどかわりません。
まず、サメの皮の道具で削ります。ザラザラ感が残るため、鋼(はがね)のやすりで形をととのえ、「とくさ」とよばれるつくしの仲間の植物できた天然のやすりで磨きます。
紙やすりでみがくと簡単なのですが、竹内さんは昔ながらのとくさにこだわります。とくさで磨くと歯の間隔が開き、表面がなめらかになるのです。
「とくさ」は「砥草」って書くんですよね。つくしのように茎が節で分かれるんですよ。ワタクシらら子の実家にも生えていて、子どもの頃は爪を磨いたり、節をばらばらにしたりして遊びました。
日本髪が生まれた江戸時代、日本髪の文化がなければこんなにつげ櫛は、発展していなかったと竹内さんは、語ります。使いやすいものはなくならない。
その時の髪型にあったものをつくり続けるのがつげぐし職人の使命だそうです。
ハマると拘るヲタクのつげ櫛コレクション
廣島つげ櫛店さんの利休ぐしと夢の櫛
上野十三やさんの中歯ぐし
つげ櫛はいいぞ!! pic.twitter.com/XUQam1tHrL— いり🍋 (@iri_kiriya) May 8, 2020
(いり🍋@iri_kiriyaさん、アップありがとうございます。)
美の壺:最後のツボ「受け継がれる江戸っ子気質」
美の壺 木戸 一江 さん 袋物博物館館長 東京・両国
江戸時代の浮世絵に描かれる小物入れやたばこ袋、シャレていますね。
東京・両国に袋物を展示する博物館「袋物博物館」があります。展示されている作品をみせていただきました。
鼻紙をいれた「紙入れ」は、開けてみると内側には、更紗や縞の布が使われています。キセルの筒がついた「たばこ入れ」は、内側に富士山の刺繍がほどされています。
底が箱型の袋には、ひも通しの部分が、鹿のツノ、クジラのヒゲが編み込まれている部分もあります。
なんだか現代では貴重なものばかりですね。
袋物博物館の館長木戸一江さんは、長年、カバンの製造販売に携わっています。
袋物の歴史と革小物の魅力を伝えたいと思い、2004年に袋物博物館を開設されました。
木戸さんは、昔のものは、重厚感があって素晴らしいといいます。
当時の職人さんが、どんな気持ちで作ったのかは、わからないが腕とハートが違う、「江戸っ子だね〜」と感じるそうです。
革小物を扱う東屋さん(両国)
お得に素敵な商品を買えるチャンスです!
2階の袋物博物館も見応えたっぷり👀✨ https://t.co/tCLC1mckcO pic.twitter.com/TDR39g9CNa— ものづくりのまち すみだ (@mono_sumida) November 21, 2020
(ものづくりのまち すみだ@mono_sumidaさん、アップありがとうございます。)
美の壺 髙林 晋(たかばやし すすむ) さん 職人 東京・日本橋
芝居小屋や花街が近くにある東京・日本橋は、粋なまちとして知られています。
江戸時代の染めものや伝統を今に伝えている「濱甼高虎(はまちょうたかとら)」は、手ぬぐいや法被(はっぴ)と同時に多くの袋物もあつかっています。
中でも人気のあるのが「合切袋(がっさいぶくろ)」です。
職人の髙林晋さんによると、名の由来は、いっさいがっさいの物を入れるから合切ぶくろというそうです。へぇー。
火災が多い江戸のまち、木造の家に燃えてしまってもこれを持って逃げたらなんとかなるだろうという袋だったそうです。
感覚が江戸っ子だわ~。名前もユニークですね。
濱甼高虎(はまちょうたかとら)は、昔ながらの染工法をもちいて製作販売をしていています。受け継がれた絵柄は、200もあるそうです。
「判じもの」とよばれる言葉遊びがモチーフになっています。
「堪忍」ということばが染められた袋は、その名の通り「堪忍袋(かんにんぶくろ)」、猿が5匹で「ご縁」だそうです。
江戸のシャレがいっぱいですね。
袋の裏には名前や文字が入れられる「二丁札」、袋の内側には、唐桟の縞模様です。チラリとみえるところがいいですね。
人と同じが許されない、自分だけの美学のようなものが求められる「袋」だそうです。
作り手として、手で描き、彫り、染め、仕立てるといった今までどおりの部分をなくさない髙林さんなりの美学も語っていただきました。
たずさわる人々の心意気に江戸っ子のスピリットを感じました。
今日、高虎さんに伺ってお買い物をしてきたわ(о´∀`о)ななめ掛けと合切袋(≧▽≦)判事絵☆ひょうたん3つで3拍子そろった\(^o^)/骸骨がタバコ吸ってて骨休み(゜∇^d)!!お店の人がいろいろと教えてくれた~(о´∀`о) pic.twitter.com/CjVqYy2ejg
— めちゃこですっ (@mechako_de_su) September 5, 2020
(めちゃこですっ@mechako_de_suさん、アップありがとうございます。)
美の壺:再放送・バックナンバー情報
NHK美の壺の【バックナンバー】をまとめてみました。
2019年以降の放送一覧のまとめはこちら。
2022 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2021 年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2020年はBSプレ・Eテレともにこちらが放送一覧です。
2019年はこちらです。
ご参考になさってくださいね。